1089ブログ
特別展「コルカタ・インド博物館所蔵 インドの仏 仏教美術の源流」 記者発表会
東京国立博物館では、2015年3月17日(火)~5月17日(日)、表慶館にて特別展「コルカタ・インド博物館所蔵 インドの仏 仏教美術の源流」を開催します。
展覧会開催に先立ち、11月7日(金)、報道発表会を行いました。

コルカタ・インド博物館所蔵 インドの仏 仏教美術の源流
会場は、なんとインド大使館。そうそう足を踏み入れることのない場所だけに、緊張もし、また晴れやかな気持ちもいたします。インド大使館のご厚意に深く感謝申し上げます。
おかげさまで会場は、プレス関係の方々でほぼ満席の状態でした。
この展覧会は、インド政府が主体となって開催されるアジア国際巡回展で、「日本に於けるインド祭2014-15」の主要な文化交流イベントとしても位置づけられています。
発表会のはじめに、ディーパ・ゴパラン・ワドワ駐日インド大使よりご挨拶いただき、当館の銭谷眞美館長からは挨拶と本展の意義が語られました。
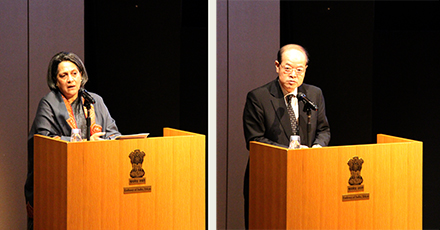
(写真左)ディーパ・ゴパラン・ワドワ駐日インド大使
(写真右)銭谷眞美東京国立博物館館長
続いて、展覧会ワーキンググループのチーフである小泉惠英企画課長が、展覧会の概要を説明しました。
冒頭こそ「いささか緊張しております」でしたが、しかしインド仏教美術は小泉の専門領域であり、まさにストライクゾーン。説明もしだいに熱を帯びてきます。

小泉惠英企画課長
本展では、アジア最古の博物館(1814年創立)であるコルカタ・インド博物館から、仏教美術作品およそ90点が来日、展示されることとなります。
インドを代表する博物館が所蔵する名品の数々によって、インド仏教美術の発生と歴史をたどります。
ここで主要な作品をご紹介します。
古代初期の仏教寺院は、ストゥーパ(仏塔)を中心に造営されました。インド中部のバールフット・ストゥーパ遺跡の品々は、コルカタ・インド博物館で最も著名なコレクション。ストゥーパの周りを囲っていた欄楯(らんじゅん)には、ブッダ(釈迦如来)の生涯や前世の行いなど、さまざまなストーリーが、石の浮き彫りで、いきいきと表されています。
この時代(紀元前2世紀ごろ)、ブッダはいまだ人形(ひとがた)に表象されることが一般ではなく、下の写真にみるような樹木や、法輪、足跡などで象徴的に表されていました。
人々が菩提樹(ぼだいじゅ)に向かって礼拝をしているのがわかります。

菩提樹(カナカムニ仏)の礼拝 バールフット出土 ジュンガ期(紀元前2世紀) インド・コルカタ博物館所蔵
ブッダの像を人の似姿(にすがた)に造形するようになるのは1世紀ごろ。現在のパキスタンにあるガンダーラや、北インドのマトゥラーで、ほぼ同時期に作られ始めたとされます。
大乗仏教の発展にともない、釈迦をはじめとする阿弥陀や薬師などの如来、観音や弥勒(みろく)などの菩薩の像も造られていきました。
写真のような、みずみずしい肉体をもったマトゥラーの仏像、荘重で洗練された姿を見せるガンダーラの仏像です。

(写真左)仏坐像 アヒチャトラー出土 クシャーン朝(1世紀頃) インド・コルカタ博物館所蔵
(写真右)弥勒菩薩坐像 ロリアン・タンガイ出土 クシャーン朝(2世紀頃) インド・コルカタ博物館所蔵
5~6世紀には仏教の中に密教が萌芽し、バラモン教やヒンドゥー教の神々をも取り込んで、多様な仏たちが次々と登場していきます。8世紀、東インドに興ったパーラ朝では、仏教が手厚く保護され、密教が信仰されました。下の写真で中央に立つのは密教において多彩な変化身を展開した観音菩薩の一つ。
上部には大日・宝生(ほうしょう)・阿弥陀・阿閦(あしゅく)・不空成就(ふくうじょうじゅ)の五大如来を配しています。
この五仏にピンときた貴方、そう! 言わずと知れた(ちと言い過ぎか)「金剛界五仏」(こんごうかいごぶつ)。日本の密教でも重要視される両界曼荼羅(りょうかいまんだら)のうち、金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)に描かれています。
時空を隔てた五仏の響きあいに、大いなるロマンをかきたてられませんか?(あくまで個人の感想です)
これはなんとしても、彼我の印相(いんぞう)(仏のとる手のポーズ)を比較せねば。

カサルパナ観音立像 チョウラパーラ出土 パーラ朝(11~12世紀頃) インド・コルカタ博物館所蔵
質疑応答のあと、サプライズゲストが!
芸能界きっての仏像好きで知られる、みうらじゅんさん、いとうせいこうさんの登壇です。
みうらさん、いとうさんの、インドと仏像に寄せる熱き心は、かの『見仏記』でもよく知られるところ。そしてお二人は、この日この時をもって、「インド仏像大使」に就任されることとなったのです!
オリジナルグッズのプロデュースなど、展覧会をいろんな方面から応援してくださる心強い味方です。
軽妙かつ真剣に、仏像大使就任の意気ごみを語ってくださいました。その後、ディーパ・ゴパラン・ワドワ大使からお二人に記念品が贈呈され、華やかにフォトセッションへと移ります。

前列左から、みうらじゅんさん、 いとうせいこうさん
後列左から、佐藤雅徳日本経済新聞社副社長、ディーパ・ゴパラン・ワドワ駐日インド大使、銭谷眞美東京国立博物館長
かつてインドで生まれた仏教と仏像は、東へと道をたどり日本に到達しました。
仏教を信仰した、いにしへの人々は誰しも、仏教生誕の地にはるかな憧れを抱きました。
そのインドから今、初期の仏像をはじめとする、まさに珠玉の仏教美術が、海を越えてトーハクにやってきます。
ご期待ください。
カテゴリ:news、2015年度の特別展
| 記事URL |
posted by 伊藤信二(広報室長) at 2014年11月11日 (火)
絵画を担当している沖松と申します。
開催中の「日本国宝展」では、掛け軸装の絵画作品ほとんどを奥行き20センチの薄型ケースで展示しています。
開幕時のブログでも触れられていますが、名品にこんなに近づいてご覧いただける機会は滅多にありません。
細かい描写や繊細な表現を特徴としている作品では、細部を見る楽しみというものがあります。
特に、細かな描写や微妙で美しい色使い、金箔を細く切った截金(きりかね)や彩色による繊細精緻な文様表現が見所のひとつといえる平安仏画は、間近に寄らないとその造形的魅力はなかなか伝わらないと思います。
仏画のコーナーは、展示の高さも普段より低めになっているので、ケース前に規制用の白線が引かれているとはいえ、細かい描写や表現もいつもより、かなり見やすくなっているはずです。

11月11日(火)からの後期展示作品の中では、形や色彩に対する造形感覚の繊細さという点で「虚空蔵菩薩像」が一押しです。
金箔のみ、銀箔のみ、金と金の間に銀を挟み込んだもの、というように色味の違う截金を、全体の描写の中でかなり意識的に使い分けたり、組み合わせたりしているらしいことが、近年の東京文化財研究所との共同調査によりわかってきています。

国宝 虚空蔵菩薩像 平安時代・12世紀 東京国立博物館蔵 2014年11月11日(火)~12月7日(日)
同 左膝部分の拡大 撮影:城野誠治(東京文化財研究所)
ほかに、第4章 多様化する信仰と美の会場でも絵画作品の多くを薄型ケースで展示しています。
北宋時代の仏画の名品である仁和寺の「孔雀明王像」(11月11日(火)~12月7日(日))、
京都国立博物館の雪舟筆「天橋立図」(11月26日(水)~12月7日(日))、
そして南宋絵画の名品である当館の「紅白芙蓉図」(11月11日(火)~12月7日(日))もすべて、
手に取るような距離で見ることができます。

国宝 紅白芙蓉図 李迪筆 中国・南宋時代・慶元3年(1197) 東京国立博物館蔵
2014年11月11日(火)~12月7日(日)
どうぞこの機会を逃さず、名品中の名品たちを間近でお楽しみください。
カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展
| 記事URL |
posted by 沖松健次郎(保存修復室主任研究員) at 2014年11月10日 (月)
研究員のイチオシ作品! ~東アジアの華 陶磁名品展・日本編~
ほほーい! ぼくトーハクくん!
今日は、2014年日中韓国立博物館合同企画特別展「東アジアの華 陶磁名品展」の会場から、
日本の注目作品をリポートするほ。
この展覧会を担当した横山研究員に案内してもらうほ!

![]() トーハクくん、こんにちは。展示室へようこそ!
トーハクくん、こんにちは。展示室へようこそ!
![]() 横山さん、よろしくお願いしますほ! (でれでれ)
横山さん、よろしくお願いしますほ! (でれでれ)

![]() 展覧会がはじまって1ヵ月以上経つけど、何で日本、中国、韓国が一緒に展覧会を
展覧会がはじまって1ヵ月以上経つけど、何で日本、中国、韓国が一緒に展覧会を
開催することになったんだほ?
![]() 3ヵ国の国立博物館(東京国立博物館・中国国家博物館・韓国国立中央博物館)は、
3ヵ国の国立博物館(東京国立博物館・中国国家博物館・韓国国立中央博物館)は、
約2年に1回のペースで館長会議を開催しています。
前回の会議の折に「今度は一緒に展覧会を企画しましょう」という話が持ち上がり、
日本開催となる今年の会議にあわせて、展覧会をトーハクで開くことになりました。
![]() なるほー! 記念すべき第1回なんだほ。
なるほー! 記念すべき第1回なんだほ。
![]() そうなんです。だからこそ、3ヵ国それぞれで長い歴史があり、古くから親しまれていて、
そうなんです。だからこそ、3ヵ国それぞれで長い歴史があり、古くから親しまれていて、
お互いの影響も大きい「陶磁器=やきもの」がテーマに選ばれたんです。
![]() 3ヵ国のやきものが一度に見られるなんて、すごいほ!
3ヵ国のやきものが一度に見られるなんて、すごいほ!
![]() 会場に入っていただくと、まず3館の紹介するパネルがあって、振り返ると各国の代表作が
会場に入っていただくと、まず3館の紹介するパネルがあって、振り返ると各国の代表作が
皆さんをお迎えします。
そして、展覧会全体をどーんと見渡していただけるような展示室になっています。

![]() おぉ! これは圧巻だほ! それに、赤い台が中国、緑が韓国、青が日本の作品と区別されていて、
おぉ! これは圧巻だほ! それに、赤い台が中国、緑が韓国、青が日本の作品と区別されていて、
わかりやすいほ。
![]() 中国・韓国の作品については、三笠さんが青磁への愛情たっぷりに解説してくれたので
中国・韓国の作品については、三笠さんが青磁への愛情たっぷりに解説してくれたので
今日は主に日本の作品についてご案内しますね。
日本の作品は、縄文時代の土器から江戸時代の陶磁器まで、日本の陶磁史をダイジェストで紹介する
構成になっています。
それぞれが各時代を代表する名品ばかりなのですが、今日は「茶陶」に注目しましょう。

![]() ちゃとう・・・?
ちゃとう・・・?
![]() 茶の湯に関するやきもののことね。
茶の湯に関するやきもののことね。
![]() たくさんある日本のやきものの中で、なんで茶陶が注目なんだほ?
たくさんある日本のやきものの中で、なんで茶陶が注目なんだほ?
![]() それは、茶陶が日本国内でどんどん発展していった特に「日本らしさ」の強いものだからなの。
それは、茶陶が日本国内でどんどん発展していった特に「日本らしさ」の強いものだからなの。
![]() 日本らしさ…?
日本らしさ…?
![]() 室町時代から安土桃山時代にかけて茶の湯が盛んになったことで、
室町時代から安土桃山時代にかけて茶の湯が盛んになったことで、
日本の陶磁器づくりにも大きな影響を及ぼしました。
日本の陶磁器は、中国や朝鮮半島からの技術や様式の移入によって発展してきた背景が大きいのだけれど、
お茶に関わっていくなかで、茶人たちは「こういうお茶碗がほしいな」とか
国内各地で独自性が強く発展したのよ。
茶陶はそうした背景をふまえつつ、豊かな想像力でバラエティに富んだ創造性を発揮していくのです。
たとえばこのお茶碗。


重要文化財 黒楽茶碗 銘ムキ栗 (底裏)
長次郎 安土桃山時代・16世紀
文化庁蔵
![]() わ、四角いほ!
わ、四角いほ!
![]() これは、千利休が長次郎に作らせたといわれる茶碗なの。本来であれば「丸い」お茶碗の概念を超えて、
これは、千利休が長次郎に作らせたといわれる茶碗なの。本来であれば「丸い」お茶碗の概念を超えて、
誰もが目を引く、四角というかたちが斬新でしょう?
![]() “あばんぎゃるど”だほ。
“あばんぎゃるど”だほ。
![]() それでいて角ばっていなくて、てのひらに優しく収まるという作りをしています。
それでいて角ばっていなくて、てのひらに優しく収まるという作りをしています。
使う人ならではの発想なのです。
![]() 結構考えられているんだほ。
結構考えられているんだほ。
![]() 美濃や唐津では、日本で初めて下絵付けを施したやきものが作られるのですが、
美濃や唐津では、日本で初めて下絵付けを施したやきものが作られるのですが、
その新たな技術をおしみなく発揮して、懐石のうつわがのびやかに作られています。


重要文化財 鼠志野草花図鉢 重要文化財 銹絵芦図大皿
美濃 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 唐津 江戸時代・17世紀
文化庁蔵 文化庁蔵
![]() それから、この蓋物のような織部は、「桃山様式」と呼ばれる独創的な茶陶の代表選手といえます。
それから、この蓋物のような織部は、「桃山様式」と呼ばれる独創的な茶陶の代表選手といえます。

織部扇形蓋物
美濃 江戸時代・17世紀
東京国立博物館蔵
![]() 緑色の部分と茶色い模様が交互になっていて、おもしろいほ。
緑色の部分と茶色い模様が交互になっていて、おもしろいほ。
扇のかたちも、すごく日本らしいほ。
![]() そう、そうなの! トーハクくん、いいところに着目しています!
そう、そうなの! トーハクくん、いいところに着目しています!
![]() そんなに褒められると照れるほ~(でれでれ)。
そんなに褒められると照れるほ~(でれでれ)。
![]() 緑色のくすり(釉薬(ゆうやく))と茶色(鉄絵(てつえ))の技術はずっと前からあるものだけれど、
緑色のくすり(釉薬(ゆうやく))と茶色(鉄絵(てつえ))の技術はずっと前からあるものだけれど、
これを「片身替わり」と呼ばれる、染織や漆工で流行していたデザインにならって表しているの。
扇というかたちも、先ほどの茶碗同様、うつわの基本的な「丸」のかたちにとらわれない奇抜さで個性的でしょ。
![]() (ほめられて良い気分~♪)なんだか、「ちゃとう」がとっても好きになってきたほー。
(ほめられて良い気分~♪)なんだか、「ちゃとう」がとっても好きになってきたほー。
![]() そう言ってもらえると、展覧会の担当者としてとってもうれしいです。ありがとう!
そう言ってもらえると、展覧会の担当者としてとってもうれしいです。ありがとう!

![]() (笑顔が素敵すぎるほ~!)三笠さん、横山さんのお話をまとめると、
(笑顔が素敵すぎるほ~!)三笠さん、横山さんのお話をまとめると、
今回の展覧会はそれぞれの国らしい陶磁器が出ているってことなんだほ?
![]() そうですね。出品作を選ぶにあたっても、そういうところを大切にしました。
そうですね。出品作を選ぶにあたっても、そういうところを大切にしました。
各館の陶磁器コレクションの特徴を知ってもらいつつ、
技術や様式の伝わり方、影響なども感じてもらえるといいなと思います。
3ヵ国合同の企画という、意義のある展覧会としてたくさんの方に見ていただきたいです。
![]() 横山さん、ありがほーございました!
横山さん、ありがほーございました!
カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展
| 記事URL |
posted by 横山梓(特別展室研究員) at 2014年11月07日 (金)
特集「西日本の埴輪 -畿内・大王陵古墳の周辺-」の見方3-造形・変遷編-
本特集「西日本の埴輪-畿内・大王陵古墳の周辺」(2014年9月9日(火)~12月7日(日):平成館考古展示室)も、残すところ1ヶ月余りとなりました。
今回の特集展示では、普段、当館ではなかなかお目にかけることができない(畿内地方最盛期の)“本場”の埴輪をご覧頂いています。

展示全景
もちろん、畿内地方の円筒埴輪の雄大な大きさや、人物埴輪・動物埴輪の秀逸な造形も大変魅力的です。
しかしながら、当館の人気者(?)で、独特の“風合い”を感じさせる関東地方を中心とした人物・動物埴輪との関係に、想い(疑問?)が及んだ方も多いかと思います。
今回は、その誕生の“秘密”についてお話しします。
第1回で紹介しましたように、埴輪には主な種類だけでも、実に多種多様な器種があります。
もちろん、古墳に配列される場合は円筒埴輪・壺形埴輪などが圧倒的多数を占めます。
しかし、古墳時代前期から中期(4世紀中頃~5世紀初頃)にかけて、実にさまざまな器財埴輪や人物・動物埴輪などが次々と出現し、次第に種類が増えていったことが明らかにされています。
その造形には、製作技術が異なる二つの大きな“潮流”がありました。
まず、最初に誕生したのは、いわば“土器系の埴輪”です。
埴輪の起原は、弥生土器が変化して誕生した円筒埴輪や壺形埴輪で、後にこれらを組み合わせた朝顔形埴輪も登場しました。瀬戸内から近畿地方で成立したとみられています。
その誕生からおよそ100年後、次に出現したのはさまざまな道具(器物)を表現した器財埴輪でした。
4世紀中頃に現れた家形埴輪に続いて、貴人に差しかける日傘を象った蓋形埴輪をはじめ、武器・武具を象った甲冑・盾・靫形埴輪や船形埴輪などが、次々と登場したことはすでにご紹介したとおりです。
このうち、“土器系の埴輪”(円筒埴輪・壺形埴輪・朝顔形埴輪)は、第2回で解説しましたように、粘土紐を巻き上げる技法で造られています。
縄文・弥生時代以来の伝統的な土器造りの製作技術で作られた埴輪です。
これに対し、器財埴輪は粘土板を多用し、輪郭を刀子状の工具で切り抜くように整形した、実にメリハリ(!)の効いた造形が特色です。
船形埴輪の舳先(へさき)・艫(とも)にそそり立つ飾板や、家形埴輪の破風(はふ)や軒先(のきさき)にみられるシャープな輪郭からは、その造形技法の鋭さを感じ取って頂けるものと思います。

(左) 重要文化財 埴輪 船 古墳時代・5世紀 宮崎県西都市 西都原古墳群出土
(右) 重要文化財 埴輪 入母屋造家 古墳時代・4~5世紀 奈良県桜井市外山出土
一方、中期から後期(5世紀後半~6世紀初頃)にかけては、新たに人物・動物埴輪や水鳥形埴輪などの多様な形象埴輪が出現しました。
これらの埴輪は、細部には人物の服飾や頭髪などに写実的な部分も見られますが、基本的には円筒形を基本にしていることが特徴です。
人物・動物の胴部や頭部は、円筒埴輪・壺形埴輪などの“土器系”の埴輪と同じく、粘土紐巻き上げを基本とする製作技術で作られています。
そのため、外形の輪郭は丸みを滞びた滑らかなカーブを描き、全体に柔らかな造形が特色です。
とくに、人物埴輪は器台部から頭部に向かって、粘土紐を繰り返し巻き上げることで製作されています。
その結果、下半部は上半部を支える“土台”の役割を果たすため、上半身は一般的に下半身に比べて「小振り」に製作されていることに特徴があります。
多くはしっかりとした下半身や胴体部分の表現に比べ、頭部は小さめの表現が印象的です。
すでにお気づきのように・・・、人物埴輪の頭部が“小顔”で愛らしいことには、必然的な理由(!)があった訳です。

(左) 埴輪 猪 古墳時代・5世紀 大阪府藤井寺市 青山4号墳出土 大阪府立近つ飛鳥博物館蔵
(右) 埴輪 女子(巫女) 古墳時代・5世紀 大阪府藤井寺市 蕃上山古墳出土 大阪府立近つ飛鳥博物館蔵
また、ほぼ同じ時期の器財埴輪にも、製作技術上の変化を認めることができます。
家形埴輪に代表されるように粘土板と刀子状工具の使用が衰退し、同じく粘土紐巻き上げ技法を基本とするようになります。
もともと家形埴輪は建築物を象った埴輪ですので、“角張った”外形と必要な室内空間から生み出されたバランスのよいシルエットが特徴でした。
しかし、この時期の家形埴輪は、壁の隅部が著しく丸みを帯びた形に変化していることがお判り頂けると思います。
必要以上にずいぶんと“ノッポ”な外形で、まるで西洋の教会建築を思わせるような外観です。
とくに屋根部は、実際の建物ではあり得ないような傾斜をもつ例が増加し、これも壁部の変化に呼応した変化と考えられます。
とりわけ、6世紀後半の関東地方の家形埴輪の中には壁部分が“円筒化”し、断面形がほとんど楕円形(!)に近い例まで現れます。
とても、実際の建物を写実的に表現していると考えることはできません。

(左)埴輪 寄棟造家 古墳時代・5~6世紀 奈良県磯城郡三宅町石見出土
(中)埴輪 寄棟造倉庫 古墳時代・6世紀 群馬県伊勢崎市上植木出土
(右)埴輪 切妻造家 古墳時代・6世紀 群馬県桐生市新里町出土(船田祐研氏寄贈) ※この作品は現在展示されていません。
このように人物・動物埴輪の出現をきっかけに、形象埴輪には単なる写実とは異なる新たな独特の表現が生み出されました。
すると、当館の人気者の愛らしい(?)人物・動物埴輪などは、関東地方でこのような新たな表現がさらに発達して洗練された結果であったということができそうです。
いわば、新たな埴輪独自の造形表現が完成された姿ということができます。

(左)埴輪 盛装の男子 古墳時代・6世紀 群馬県太田市四ツ塚古墳出土
(中)重要文化財 埴輪 盛装の女子 古墳時代・6世紀 群馬県伊勢崎市豊城町横塚出土 ※この作品は現在展示されていません。
(右)埴輪 犬 古墳時代・6世紀 群馬県伊勢崎市大字境上武士字天神山出土
このように古墳時代後半期においても、畿内地方で生み出された形象埴輪の器種や製作技法の変化は、再び地方の埴輪生産に大きな影響を与えることになります。
やはり、畿内地方の埴輪は全国の埴輪造りの基準であり続けていたのです。
もちろん、その背景には、埴輪が古墳時代の葬送儀礼に深く関わっていた(切っても切れない関係)とみられることが、もっとも大きな要因と考えられます。
古墳時代終末期(7世紀)を迎えると、全国で造り続けられていた前方後(後方)円墳は、突然ともいえる早さで急速に築造されなくなります。
その関係性を証明(?)するかのように、あれだけ盛行していた埴輪の製作も、ほぼ同時に一切見られなくなるのです。

まさに埴輪は、日本列島独自の墓制である前方後円墳の誕生・終焉と軌を一にした、古墳文化そのものを“体現”した存在といえそうです。
それ故に通常、遺物や遺構だけでは判らない、目に見えにくい古墳文化の“風景”を後世の現代に具体的に伝えてくれます。
20世紀はしばしば「映像の世紀」ともよばれます。
歴史研究の方法として映像の果たす役割は、その再現性はもちろん、デジタル技術でカラー化が可能となった現在、ますます重要性が高まっていることをご存じの方も多いかと思います。
埴輪は、文字のない時代の人々の営み・行動(所作)を含め、当時の人々と道具などの関係性(情景)を造形(3D)で伝えてくれる、実に貴重な「証言者」ともいえる存在なのです。
このように多種多様な埴輪の一見素朴な味わいの外観と魅力的な造形には、古くから多くの方が惹きつけられてきました。
しかし、その誕生と移り変わりの背景には、当時の社会や人々の行動を考える多くのヒントが隠されていました。
本特集展示をとおして、埴輪のもつ独特な造形とその変化に秘められた「時代のうねり」や、(まさに“3D化”された・・・)「当時の人々のメッセージ」を感じ取って頂ければ幸いです。
ギャラリートーク
「円筒埴輪と形象埴輪の見方」 2014年11月7日(金) 18:30~19:00 東洋館ミュージアムシアター
| 記事URL |
posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2014年11月05日 (水)
研究員のイチオシ作品! ~東アジアの華 陶磁名品展・韓国編~
2014年日中韓国立博物館合同企画特別展「東アジアの華 陶磁名品展」の
見どころのひとつとして、韓国国立中央博物館から出品された
高麗(こうらい)(918~1392)の貴重な青磁が挙げられます。
日本において貴族に代わり武士が台頭し、政治や文化の担い手として動き出した12世紀、
中国と朝鮮半島では格調高い青磁がつくり出されました。
それが、北宋(960~1127)の汝窯(じょよう)青磁、そして高麗の「翡色(ひしょく)」青磁です。
「翡色」青磁について有名なエピソードがあります。
1123年(宣和5)、北宋末の皇帝、徽宗(きそう)の時代。
徐兢(じょきょう)という人物が高麗を訪れ、見聞を記しました(『高麗図経』)。
このなかで彼は高麗には青くて美しいやきものがあり、「翡色」と呼ばれていると
驚きをもって伝えたのです。
朝鮮半島において青磁が焼かれるようになったのは、およそ9世紀の頃。
中国江南の越窯の技術が導入されたと考えられています。
今回、中国国家博物館から出品された2級文物「青磁碗」。唐(618~907)の宮廷に納められ、
「秘色(ひしょく)」と呼ばれたこの美しい青磁を焼いたあの越窯です。
初めは中国の技法に倣った製品がつくられていましたが、次第に独自に洗練された姿となりました。
飲食の器、祭器、文房具、化粧道具など種類は多岐にわたり、高麗の高貴な人々に大変愛された
器であったことがわかります。
そして、その美しさは青磁を生んだ地、中国の人々をも驚かせるものであったのです。
それは天下の汝窯青磁とならび称されました。
特別展「台北 國立故宮博物院―神品至宝―」に出品されていた汝窯青磁と比べてみると、
白玉にたとえられる汝窯青磁の釉色とは異なり、「翡色」青磁の釉色はつややかで
透明度が高く、それでいて深みのある青色。落ち着きがあって気品漂う色調です。
精巧な形もまた魅力的です。いかにも貴族好みの薄く軽やかな形(写真1)や、
可塑性をいかして獅子や麒麟、亀、龍などの形をした器(写真2、3)もつくられました。

(写真1) 青磁輪花皿
伝黄海北道開城付近出土 高麗時代・12世紀
韓国国立中央博物館蔵

(写真2) 国宝96号 青磁亀形水注
黄海北道開城付近出土 高麗時代・12世紀
韓国国立中央博物館蔵

(写真3) 青磁双龍筆架
黄海北道開城付近出土 高麗時代・12世紀
韓国国立中央博物館蔵
このようなきわめて複雑な形の器は、中国青磁の模倣から解き放たれ、
自由で充実した造形感覚をもってうみ出された高麗青磁独自の姿といえます。
高麗青磁の特性は、装飾にもみてとることができます。
線刻や貼付け、鉄絵を施したものがみられますが、とりわけ注目されるのは
素地に彫り文様をあらわし、凹部分に白や赤(黒色を呈する)の色の異なる土を埋めて
青磁釉を掛けて焼きあげる象嵌(ぞうがん)青磁。

青磁象嵌牡丹文枕
黄海北道開城付近出土 高麗時代・13世紀
韓国国立中央博物館蔵
金工の技法を青磁に応用したもので、12世紀後半~13世紀に盛期を迎えたこの象嵌装飾は、
洗練された形、静謐な翡色の釉調と見事に調和しています。
汝窯や官窯、龍泉窯など釉調にこだわり、その色や表情、質感を追求した中国青磁と、
さまざまな技法をもちいて器面を華麗に装ってゆく高麗青磁。
東アジアではこのように性質を異としながらも、権力者はじめ多くの人々を虜にした
きわめて美しい青磁がまさに同じ頃に花開いたのです。

陶磁器の研究もさかんに行なわれている韓国国立中央博物館
今回の展示は小規模ながら、このように見どころのある高麗青磁の名品を
お借りすることができました。
「翡色」青磁の生みの親ともいうべき、中国・越窯の「秘色」青磁とならんで
展示されるのも、3国合同企画ならではのこと。
またとない貴重な機会、ぜひお見逃しなく。
カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展
| 記事URL |
posted by 三笠景子(保存修復室研究員) at 2014年10月31日 (金)

