1089ブログ
このたび開催中の特別展「台北 國立故宮博物院―神品至宝―」の準備にあたり、3回にわたって台北故宮を訪問し、作品を調査させていただく機会がありました。

中国・宋(960~1279)、明(1368~1644)、そして清(1644~1911)の皇帝たちのためにつくられた第一級の作品を、実際に手にとる。心臓が止まりそうなくらい緊張しましたが、研究員冥利に尽きる至福の時間でした。
それらを手にとって驚いたことは、想像していた以上に軽かったり、重かったり、大きかったり、小さかったり、そして光を通すほどに薄かったということです。
たとえば汝窯(じょよう)青磁。一般的に青磁は、素地の灰色半磁質の胎土のうえに、ガラス質の釉がかかったやきものです。日本に数多く伝わっている江南、浙江(せっこう)南部にひろがった龍泉窯(りゅうせんよう)青磁の胎は堅く密に焼き締まっていて、とくに底部が厚く、安定した造形が特徴です。青磁釉は時に何層も重ね掛けされるものもあり、手にとると小さな作品でもしっかりとした重みを感じるものです。ところが、汝窯の輪花碗の場合、さらさらと乾燥した軟質の胎土で、釉はごく薄くかかっており、素地は均一に薄いため、手にとるとふわっと軽いのです。

青磁輪花碗(せいじりんかわん)
汝窯 北宋時代・11~12世紀 台北 國立故宮博物院蔵
また、見込みは吸い込まれるように深く、写真で見るよりずっと大きく感じます。輪花形の碗は、北宋時代(960~1127)に陶磁器や漆器、金属器にひろく流行した形で、見込みの深いものは湯をはって酒注を入れ、燗をするための「温碗(おんわん)」と考えられています。このように汝窯青磁は、それぞれたしかに実用に適ったシンプルな形をしています。しかし輪花碗を実際に両手にとってみると、まるで日本の楽茶碗(らくちゃわん)のように胴部の丸みがしっくりと手になじみます。北宋の皇帝、そして清(1644~1911)の乾隆帝(けんりゅうてい)はこうして手になじませてその形と色を楽しんだにちがいない。その悠然とした姿に「皇帝の器」という貫録を感じるとともに、いわゆる量産品にはない繊細さがあることがわかりました。
軽さ、薄さといえば、明時代(1368~1644)初期の景徳鎮(けいとくちん)官窯の器も驚異的です。永楽(えいらく)年製(1403~1424)の銘を持つ白磁雲龍文高足杯は、展示室のケースのなかで明るい照明を受けて、息を飲むような美しさで輝いています。

白磁雲龍文高足杯(はくじうんりゅうもんこうそくはい)
景徳鎮窯 明・永楽年間(1403~1424) 台北 國立故宮博物院蔵
紙のようにごく薄い胎には雲龍文が刻まれていますが、肉眼でもなかなかよく見えません。光に透かすとようやく見えてくるこのような装飾は「暗花(あんか)」と呼ばれます。まさに超絶技巧、とても贅沢なやきものです。
この作品のほか、宣徳(せんとく)年間(1426~1435)、成化(せいか)年間(1465~1487)につくられた青花・五彩の器には、白磁の胎が玉のようにつややかで美しく、そしてきわめて薄いものがみられます。とても陶磁器とは思えない軽さで、手に持っているのに心もとない気持ちがします。このように繊細な作品は、戦前、明初の景徳鎮窯器の実体がまだよく知られていなかった時代に形成された東京国立博物館の中国陶磁コレクションにはほとんど見ることができません。
予想以上に小さくて驚いたのは、藍地描金粉彩游魚文回転瓶です。景徳鎮窯に派遣された役人、督造官(とくぞうかん)の唐英(とうえい)が、乾隆帝のために開発した究極の陶磁器です。今回の展覧会の注目作品の一つです。

藍地描金粉彩游魚文回転瓶(らんじびょうきんふんさいゆうぎょもんかいてんへい)
景徳鎮窯 清・乾隆年間(1735~1795) 台北 國立故宮博物院蔵
吹きつけ技法による藍地の上に極細の金彩が覆う豪華な瓶。頸部を回すと、内心部に描かれた愛らしい金魚がのぞきます。この作品は対でつくられ、花器として使用する瓶であったと伝わりますが、その大きさはちょうど手におさまるサイズ。乾隆帝は手のひらにのせてくるくると回しながら、おもちゃのように遊んだに違いありません。
碗や皿を手に持たず、卓上に置いて食事をとることが基本的なマナーとされる中国や韓国とは異なり、日本では器は手を添えて使うもの。日常的にやきものの重さを感じ、ざらざら、つるつる、その質感を楽しむことを知っている日本人こそ、中国の皇帝を虜にした陶磁器のさまざまな魅力を深く味わうことができるのではないでしょうか。
カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展
| 記事URL |
posted by 三笠景子(保存修復室研究員) at 2014年08月08日 (金)
自由研究応援イベント「見て、知って、歩いて、伊能図を体感しよう!」
トーハクのTNM&TOPPANミュージアムシアターでは、よりわかりやすく文化財に親しめるよう、ナビゲーターの案内によるバーチャルリアリティー(VR)映像の上演を行っています。通常は入館料とシアター観覧料は別なのですが、夏休み期間(7月16日~8月31日)は小・中学生料金を無料としています。ぜひこの機会に足を運んでください。
期間中の上演作品は「DOGU 縄文人が込めたメッセージ」と「伊能忠敬の日本図」。どちらもお子様が楽しめる内容となっていますが、「伊能忠敬の日本図」では、さらに自由研究応援として「見て、知って、歩いて、伊能図を体感しよう!」と題した親子向けのイベントを用意。楽しみながら学べるので、夏休みの自由研究にぴったりです。
ぜひ皆さんにも体験していただいきたいので、実際の様子を交えて紹介したいと思います。
VR作品「伊能忠敬の日本図」
2014年7月1日(火)~2014年8月31日(日)
伊能図は江戸時代後期に伊能忠敬が全国を歩き回って作り上げた、当時としては世界的にも精度の高い地図でした。
ミュージアムシアターでは、伊能図の全体像や背景と同時に、実際の伊能忠敬の測量方法を、ナビゲーターの実演を交えてわかりやすく解説。測量の際に目印として使用した梵天も登場します。
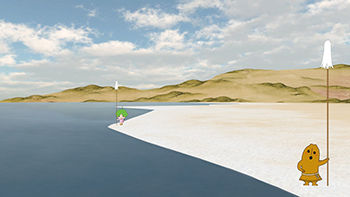
シアターではおなじみのキャラクターも登場!
インタラクティブ映像展示「不思議なライトで伊能図を見てみよう!」
2014年7月16日(火)~ 2014年8月31日(日)
ミュージアムシアター前では伊能忠敬による重要文化財「日本沿海輿地図(中図)」をスクリーンに投影しています。
そこに懐中電灯型のライトを当てると、あら不思議!現代の地図がうかびあがり、伊能図の精度の高さを実感することができます。

光をあてると何が見えるかな?
伊能忠敬 歩測ワークショップ「めざせ伊能忠敬!トーハクをはかろう!」
2014年8月1日(金)~3日(日)、2014年8月15日(金)~17日(日)
伊能忠敬が主に用いた測量法は歩いて測る「歩測」です。そのため、忠敬はいつでも同じ歩幅で歩けるよう日々訓練していたそうです。
歩測ワークショップでは、実際に自分の歩幅を測ってから歩く「歩測」を体験し、伊能忠敬の偉業を実感することができます。
 |
 |
|
| 一歩は何センチかな? | 実際に歩いてみよう! |
特集「伊能忠敬の日本図」
平成館 企画展示室 2014年6月24日(火)~ 2014年8月17日(日)
歩測を体験したあとは、実際の作品を見てみましょう。平成館1階企画展示室では、伊能忠敬が作成した地図の実物が見られます。

実物を見ると忠敬の苦労がわかるかも
伊能忠敬は日本全国を歩いて正確な日本地図を作りました。それは気が遠くなるような途方もない作業だったと思います。
今回のイベントを通して、忠敬が成し遂げた日本地図作成を親子で楽しみながら、少しでも関心を持っていただけばと考えています。また、夏休みの自由研究のヒントになればうれしいです。
| 記事URL |
posted by 関谷泰弘(総務課) at 2014年07月30日 (水)
本日より、東京国立博物館と台東区立書道博物館との連携企画、特集「趙之謙の書画と北魏の書-悲盦没後130年-」が東洋館8室で始まりました。これに先立ち、7月28日(月)には報道内覧会を開催し、多くの報道関係者にお越しいただきました。
趙之謙(ちょうしけん)は、清時代の中期、新しい書風を確立し、日本にもファンの多い書家の1人です。
裕福な家庭に生まれるものの10代には貧困を余儀なくされ、その後勉学に励みながら結婚するも、荒れた時代を背景に妻子をなくし絶望を味わうことになります。
ここで趙家の復興を誓い、高級官僚になるべく何度も試験に挑戦しますが、落第を繰り返すばかり。
やがては地方官として赴任しますが、それまでの過労がたたり56歳で生涯の幕を閉じるという、まさに波乱万丈の人生を送った人でした。
このような生涯を送った趙之謙は、多くの書の名作を残しました。
彼は受験のため北京に滞在しますが、滞在中に北魏時代の書に心酔し、後に「北魏書」と呼ばれる独特で新しい表現の確立に至るのです。
これこそが、その後の書家に多大な影響を与え、みなの心を虜にし、趙之謙の名を現在にも残すことになった理由です。
自身が特に気に入ったという肖像画から始まり、中には50年ぶりに展示が叶ったもの、同じ題材ながら所蔵の違う2件が並べられるなど、それはそれは見ごたえのある北魏の書の空間になっています。

後ろに見える作品はどちらも「四時花卉図四屏」といい、趙之謙が42歳(1870年)のときの作品です。右の4幅はトーハクが所蔵し、左の4幅は大阪市立美術館が所蔵しています。
同じ期間中、台東区立書道博物館でも同名の展覧会が開催されています。
皆さんもぜひ、両館を通して彼の生涯とその魅力をご堪能ください。
特集「趙之謙の書画と北魏の書-悲盦没後130年-」
東洋館 8室 2014年7月29日(火) ~ 2014年9月28日(日)
(前期:7月29日~8月24日、後期:8月26日~9月28日)
台東区立書道博物館 特別展「趙之謙の書画と北魏の書-悲盦没後130年-」
中村不折記念館 2014年7月29日(火) ~ 9月28日(日)
(前期:7月29日~8月24日、後期:8月26日~9月28日)
| 記事URL |
posted by 宇野裕喜(広報室) at 2014年07月29日 (火)
特別展「台北 國立故宮博物院ー神品至宝ー」の目玉のひとつ「翠玉白菜」(以下、白菜)は7月7日(月)で展示を終了しました。現在、白菜は展示されていませんが、作品をさらにじっくりとご鑑賞いただけるようになった今こそ、実は白菜の魅力をより深く知っていただくチャンスなのです。
中国で愛されつづけた玉の「ツヤ」
白菜の最大の魅力のひとつは、なんといっても「色」です。翡翠(ひすい)という石の緑の部分と白の部分を巧みに彫り分けて、一切着色することなく、白菜を本物そっくりに表現しています。

翠玉白菜(すいぎょくはくさい) 翡翠 清時代・18-19世紀 國立故宮博物院蔵 ※展示は終了いたしました
中国では、古来、「玉(ぎょく)」という美しい石をさまざまな形に彫り上げる工芸が発達しました。玉器工芸でいちばん重要だったのは、白菜のような「色」ではなく、「ツヤ」でした。
会場の前半部分に展示した玉器は、おもに宋時代(960-1279)のもの。これらの作品は、玉器の「ツヤ」が本来どのようなものであったのかをよく示しています。

鳳柄玉洗(ほうへいぎょくせん) 軟玉 南宋-元時代・12-14世紀 國立故宮博物院蔵
展示台の下に鏡を仕込んで底裏を見せています。

同 鏡に映った底部
鉱石でありながら、水気を含んでいるかのような温和な光沢。ゼラチンにも似た柔らかい透明感。光を当てるとわかるこの「ツヤ」こそ、中国の人々が愛しつづけた玉器の「生命」ともいえる質感だったのです。

龍文玉盤(りゅうもんぎょくばん) 軟玉 北宋または遼時代・10-11世紀 國立故宮博物院蔵

同 部分
中国での玉の愛好は約8千年前の新石器時代にまで遡ります。会場の後半部分では、新石器時代のものを含む太古の玉器もご覧いただけます。

会場後半にある玉器の展示
黄緑・緑・白など色はそれぞれ異なっていて、しかも、単色のものばかりですが、どの玉器も例の「ツヤ」をたたえています。
「ツヤ」から「色」へ
それでは、色よりツヤのほうが重要だった玉器に、どうして翠玉白菜のようなツートンカラーのものが出てくるのでしょうか。
今日、中国で玉と呼ばれる石材は、大きくふたつのグループに分けることができます。ひとつは「軟玉」。もうひとつは「硬玉」で、白菜の石材・翡翠も硬玉です。中国でもともと採れたのは軟玉で、潤いをたたえたあの神秘的なツヤに特徴があります。ところが、18世紀に清朝の版図が拡大すると、新しい玉材が中国にもたらされるようになりました。硬玉(翡翠)は、今日のミャンマーから運ばれてきました。鮮やかな色彩や、時おり複数の色をそなえた翡翠は、中国の人々をまたたく間に魅了しました。
おわりに 「翠玉白菜」への道
翠玉白菜の誕生には、中国における約8千年もの玉器愛好の歴史、そして250年前に起きたある変化が関わっていました。それは玉器に「ツヤ」ではなく、「色」を求めるという価値観の一大変革でした。
「神品至宝」展の会場では、新石器時代の玉器から翠玉白菜に代表される清代の玉器までの道のりを辿ることができます。白菜をご覧になった方もそうでない方も、玉器本来の神髄である柔和な光沢をその目でぜひお確かめください。白菜のはるかなる淵源に思いをめぐらせていただければ、あの緑と白の色彩が心の中でいっそう鮮明に映えることでしょう。
おまけ
それでも白菜が恋しいという方は、会場の最後に展示した「人と熊」にご注目ください。

人と熊 軟玉 清時代・18-19世紀 國立故宮博物院蔵
玉材の白い部分を人物、黒い部分を熊に彫り分けています。玉材がもつ天然の「色」を造形に活かした技法は翠玉白菜とまったく同じ。突き出たお尻と表情は愛らしく、見るものの心を癒します。

同 (別角度)
故宮での人気も上昇中で、白菜や肉形石につづく「次世代アイドル」として注目を集めています。
さらに、東洋館5階「清時代の工芸」に展示した「瑪瑙石榴(めのうざくろ)」もまた翠玉白菜と同じ技法によるものです。

瑪瑙石榴 瑪瑙 清時代・18-19世紀 東京国立博物館蔵
石榴の割れ口からのぞいた赤い果肉の一粒一粒まで本物そっくり。その迫真ぶりは決して白菜に引けを取りません。「故宮に白菜あれば、トーハクに石榴あり!」特別展のチケットで、東洋館を含む総合文化展も自由にご観覧いただけます。いまのうちにぜひトーハクの「次世代アイドル」(?)もチェックしてみてはいかがでしょうか。
カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展
| 記事URL |
posted by 川村佳男(平常展調整室主任研究員) at 2014年07月28日 (月)
特別展「台北 國立故宮博物院―神品至宝―」(6月24日(火)~9月15日(月・祝))は、
7月25日(金)午前に20万人目のお客様をお迎えしました。
多くのお客様にご来場いただきましたこと、心より御礼申し上げます。
20万人目のお客様は、目黒区よりお越しの小学6年生 辻仁志君です。
仁志君は、お母さんの智子さん、妹の祐里佳さんとご来場されました。
辻さん親子には、東京国立博物館長 銭谷眞美より、特別展図録と記念品を贈呈しました。

特別展「台北 國立故宮博物院―神品至宝―」20万人セレモニー
辻さん親子と館長の銭谷眞美(右)
7月25日(金)東京国立博物館 平成館エントランスにて
お母さんの智子さんからは、
「びっくりしました。今日は、NHKで放送されていた特番を見て、本物を見たいと思って来ました。
藍地描金粉彩游魚文回転瓶(らんじびょうきんふんさいゆうぎょもんかいてんへい)などをとくに楽しみにしています。」と、お話いただきました。
8月3日(日)で前期展示が終了し、8月5日(火)からは、書の目玉作品、蘇軾(そしょく)筆「行書黄州寒食詩巻(ぎょうしょこうしゅうかんしょくしかん)」が展示されます。
この作品は東京国立博物館のみの展示となりますので、お見逃しのないよう、ご来館をお待ちしています。
カテゴリ:news、2014年度の特別展
| 記事URL |
posted by 田村淳朗(広報室) at 2014年07月25日 (金)

