- TOP
- 1089ブログ
1089ブログ
デュシャンをみる〈考える〉ことで、日本美術を考える〈みる〉ことはできようか?
今年は、デュシャン没後50年にあたります。特別展「マルセル・デュシャンと日本美術」(2018年10月2日(火)~12月9日(日))にも、連日多くの皆さまにご来場いただいており、ありがたいかぎりです。
第1部の展示の最後に《遺作》映像をみ終わると、頭の中は「デュシャン」の世界でいっぱいになって、「デュシャン脳」になってしまったのではないでしょうか。会場隅にある消火器をみても、「レディメイド?」と思ってしまうくらい、デュシャン作品の印象が強く、さまざまな思いがめぐっているのではと思います。
続く第2部「デュシャンの向こうに日本がみえる。」は、当館所蔵の日本美術の作品を展示しています。頭の中が「デュシャン」に占拠されている状態のまま、日本美術の作品をみたらどうなるか、という試みです。日本美術がデュシャンに先じているとか、デュシャンの作品と日本美術を「比較」してどちらが優れているか、という表層的なことを推奨しているわけではありません。
古く日本でつくられたものは、もともと西洋社会と異なる価値観で培われてきたものです。しかしその多くが現在は、美術館や博物館という場所で飾られ、ケースに入れられ、うやうやしく展示する、という形式でご覧になることが多くなっていると思います。
国宝や重要文化財という価値付けがなされているものや、教科書に載っていて多くの人が知っている文化財を、展示室で確認し、安心するということにも意味はあるでしょう。しかし、この展覧会では、また違った視点から日本美術を見てもらえればと思っています。
今回、デュシャンの世界を堪能されるたことで、「作品」「芸術」「アート」「美」ってなんだろう、ということも含めてさまざまに「考えて」いただける機会ですので、第2部ではデュシャンに浸った目を踏まえながら、5つのテーマを設けて各作品を紹介しています。
まず、第2部に向かう通路の突き当たりは「黒楽茶碗 銘 むかし咄」です。
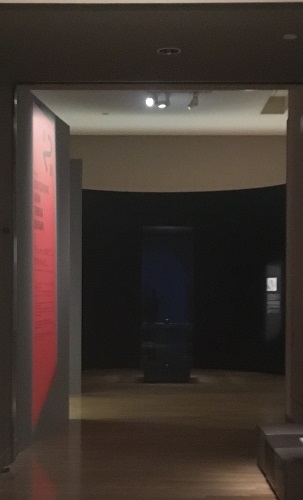
網膜に映る像を拒否する茶碗
第1章「400年前のレディメイド」では、この黒楽茶碗と伝利休作「竹一重切花入 銘 園城寺」を展示しています。利休は唐物という高価な将来品で設えるものであった茶室の世界に、そこいらにあった竹を「ただ」切って花入としたり、また、真っ黒で手の感触が残ったような手づくねの楽茶碗を用いたりしました。利休が示したものは、竹や土がもともと持っていた価値の位相を、著しく変えてしまったといえるでしょう。

意外に大きな竹の筒
第2章「日本のリアリズム」は、浮世絵の中でも異端といえる写楽の作品と、より伝統的な浮世絵版画を合わせて展示しています。
浮世絵に描かれる人物の中でも役者絵は今でいうブロマイド(今時あるのかわからないですが、芸能人の生写真みたいなものでしょうか)で、役者の「かっこいい」姿が期待されます。ところが、写楽はより実物の特徴をはっきりと表して役者の顔を描きました。ちょっと大きすぎる鼻だったり、しゃくれた顎だったり。いまならフォトショで修正するところかもしれません。当時も多くの浮世絵は理想化(修正後)されたステキな姿を表していますが、写楽の役者絵は決してそうした姿ではありません。写楽は目に見えない、役者の内面が現れる表情を写そうとしたのでしょうか。デュシャンは目に見えないものを表現しようとしたかもしれませんが、写楽はそれまでの浮世絵における人物表現の枠から飛び出した役者を描いています。


写楽(向かって右)と国政(同左)が描いた同じ四世岩井半四郎。
ご本人はどちらを気にいったでしょうか。
第3章「日本の時間の進み方」は、絵画空間に「時間」を表現した絵巻を取り上げました。第1部第1章の《階段を降りる裸体 No. 2》では、人が階段を降りる様子が1画面に表されています。古く西洋でも同一場面に異なる時間を収めた絵画は、しばしば描かれていますが、近代ではその手法は取り上げられなくなりました。一方、日本の絵巻は古来、長い画面に同じ人物が時間を追って描かれる「異時同図法」と呼ばれる手法で、絵画の中に時間の経過を表しています。絵巻は本来、少しずつ順に開いて場面ごとに見ていくもので、展示しているようにすべての部分を一度に見るものではありません。1場面ずつ見てゆくことを想像しながら横長の絵をみてゆくにつれ物語が動き出すように見えてくる感覚が生じます。

酒吞童子絵巻 巻下(部分) 鬼の首が斬られ、その首が頼光を襲う
第4章は「オリジナルとコピー」です。「コピー」というと「真似」「模倣」として、価値を低くみることもあります。しかし古来芸術家は、ほぼ先達を「倣って」作品をつくってきました。日本の絵画でも、描く主題、またその表し方も「型」があって、絵師はその型を勉強し、繰り返し師匠や私淑する絵師の「作品」を模倣し、描き方と技術を身に着け、自身の作品を生み出しています。西洋絵画でも古典絵画であれば同様です。つまり「オリジナル」は「コピー」であり、その「コピー」もまた次の世代にとっては「オリジナル」となります。つまり、いわゆる「原品」であることが芸術的価値の高さを示すものではないといえます。
デュシャンはレディメイドのレプリカを作り、「デュシャン」という署名を記します(自身で書いたものばかりでない)。サインが、そのレプリカに記されている、ということのほうに大きな意味があります。そして日本の絵画でも作られた作品の形ではなく、「誰」が作ったか(「雪舟」が描いた、など)ということのほうがもっと重要なのです。

第4章「龍図」展示風景 (右)俵屋宗達筆 (左)狩野探幽筆
最後は第5章「書という芸術」です。東洋では書は伝統的に造形上の最高位に置かれ、絵画や立体作品の上とされました。
江戸時代の本阿弥光悦は「寛永の三筆」といわれた能書家です。その書は書かれた内容をただ「読む」のではなく、筆勢や墨の濃淡のリズムを感じ、下絵とされた絵との調和を味わう総合芸術となっています。
書は文字であるため、字を読もうとしてしまうのですが、「摺下絵和歌巻」をみてみると、全体の調和や墨色によるリズムもみえてきます。
デュシャンのたとえば《The》という作品で「The」の部分を★に変えたものや、目に映ったものを描いたわけではなく、概念〈コンセプト〉を表した《大ガラス》のような作品
を経験した後だと、字をみて内容を追わない見方も楽しめるかもしれません。

摺下絵和歌巻(部分)本阿弥光悦筆
「袖」の字など濃い墨で書かれ、画面構成にリズムを生んでいる
デュシャンを通して日本美術をみる、あるいはその後もう一度、デュシャンに戻って考える、など、さまざまな「視点」から、デュシャンと日本美術をみて、考える楽しみを味わっていただければ、と思います。
デュシャンをきっかけにトーハクをより楽しんでいただければ幸いです。
カテゴリ:2018年度の特別展
| 記事URL |
posted by 松嶋雅人(研究員・本展ワーキンググループチーフ) at 2018年11月30日 (金)
- 「はにわ」 (6)
- 「内藤礼」 (4)
- 「大覚寺」 (1)
- 「法然と極楽浄土」 (5)
- 「神護寺」 (8)
- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)
- 「やまと絵」 (6)
- 「中尊寺金色堂」 (8)
- 「京都・南山城の仏像」 (4)
- 「古代メキシコ」 (6)
- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)
- 「東福寺」 (6)
- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)
- 研究員のイチオシ (559)
- 催し物 (83)
- news (328)
- 特集・特別公開 (225)
- 特別企画 (31)
- 東京国立博物館創立150年 (18)
- 絵画 (41)
- 彫刻 (80)
- 刀剣 (1)
- 書跡 (52)
- 工芸 (28)
- 考古 (81)
- 中国の絵画・書跡 (73)
- 教育普及 (105)
- 保存と修理 (22)
- 調査・研究 (6)
- トーハクくん&ユリノキちゃん (65)
- トーハクよもやま (4)
- 博物館でお花見を (21)
- 博物館に初もうで (25)
- 博物館でアジアの旅 (44)
- 展示環境・たてもの (47)
- 2022年度の特別展 (31)
- 2021年度の特別展 (21)
- 2020年度の特別展 (14)
- 2019年度の特別展 (46)
- 2018年度の特別展 (34)
- 2017年度の特別展 (37)
- 2016年度の特別展 (54)
- 2015年度の特別展 (58)
- 2014年度の特別展 (50)
- 2013年度の特別展 (67)
- 2012年度の特別展 (64)
- 2011年度の特別展 (45)
- ウェブおすすめコンテンツ (19)
- ロケ情報 (2)
- 秋の特別公開 (11)
- トーハク140周年 (16)
