- TOP
- 1089ブログ
1089ブログ
調査速報! 像内納入品が判明 大覚寺軍荼利明王
現在開催中の開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」(2025年3月16日(日)まで)には、連日多くのお客様にお越しいただいており、展覧会担当の一人として大変嬉しく思っております。

特別展「旧嵯峨御所 大覚寺」第一会場 展示風景
大覚寺は、平安時代初めに営まれた嵯峨天皇の離宮・嵯峨院を前身とします。真言宗の開祖・空海と深い交流があった嵯峨天皇は、空海の勧めで嵯峨院に持仏堂を建てて五大明王像(現存せず)を安置したといいます。それを受け継ぐ現在の本尊の五大明王像も本展で公開されています。東京で5体そろって公開されるのは初めてのことです。

重要文化財 五大明王像 明円作 安元3年(1177) 京都・大覚寺蔵
左から:大威徳明王、軍荼利明王、不動明王、降三世明王、金剛夜叉明王
この五大明王像は、金剛夜叉明王(写真右端)と軍荼利明王(写真左から2番目)の台座に記された銘文により、安元2~3年(1176~77)にかけて仏師明円(?~1199頃)が作ったことが知られています。仏像の制作年や作者が分かる例は非常に少なく、その両方が分かる大覚寺の五大明王像は大変貴重です。
ところで、当館は文化財用のX線CTスキャン装置を所有しています。この装置で360度様々な角度から撮影した多数のX線画像データをコンピューター上で組み合わせて、3Dなどの立体的なデータとして見ることができます。それにより、文化財の構造や保存状態、内部に空洞があればその様子などを知ることができます。

軍荼利明王のX線断層(CT)調査風景
本展に際して、この五大明王像5体すべてにX線断層(CT)調査を行なったところ、軍荼利明王1体にのみ、像内に納入品があることが分かりました。
ここでは調査速報として、簡単ではありますがその納入品について紹介していきます。
 軍荼利明王 頭部 垂直側断面
軍荼利明王 頭部 垂直側断面
同 納入品 3D画像
納入品というのがこの頭部内の画像に映る木柱(高さ約15cm)です。表面に何も塗ったりせずに素地のまま仕上げ、像の首の下あたりで木柱の根元を木釘で打ち付けて固定しています。
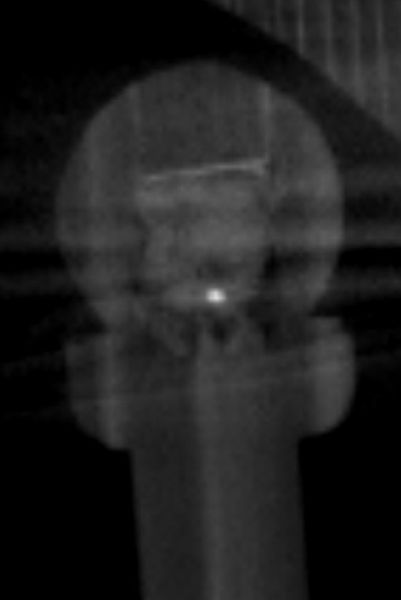
同 納入品 頂部 垂直側断面
木柱の頂部を蓮台および球状(最大径約1.4㎝、宝珠または月輪か)のかたちに作り、その中央部分を空洞にして蓋をしています。その空洞のなかに、紙と思われるものとともに、ひと際白く見える粒状のものが映るのがお分かりになりますでしょうか。これは舎利として信仰された鉱物と思われるものです。
舎利とは仏教を開いた釈迦の遺骨のこと。仏像の像内に納める例は、奈良時代にいくつか見られるものの12世紀前半までは少なく、12世紀後半以降に増えていきます。大覚寺軍荼利明王が作られたのはその12世紀後半に含まれる年代ですので、まさに舎利を仏像の像内に納めることへの関心や事例が高まる時期に作られ、かつ年代が明らかな重要な例です。しかも、木柱の頂部のなかに舎利を納める点や、木柱を打ち付けて固定する点など、入念な作りが特徴です。
なぜ舎利を納めたのか、なぜ軍荼利明王だけなのか、他の4体にはもともと納入品がなかったのか(過去の修理などで納入品が取り出されていないのか)、なぜ木柱の頂部に舎利を納めるという入念な作りにしたのか。今回の調査で像内納入品の存在が判明したことによって、新たな疑問も生まれてきました。引き続き、このような疑問や納入品の詳細、納入の目的について調べることで、大覚寺の五大明王像が作られた背景を解明する手掛かりになることが期待されます。

軍荼利明王 展示風景
文化財の調査研究において、このように最新の科学的手法を用いることで新たな情報が分かることもあります。ただし、調査にあたってはなによりも、所蔵者のご理解があってこそ実施できるものです。今回、五大明王像のX線断層(CT)調査の実施、および軍荼利明王の像内納入品の情報公開をお許しいただきました大覚寺の皆様に、この場をお借りしてあらためて御礼申し上げます。
| 記事URL |
posted by 増田政史(特別展室研究員) at 2025年02月17日 (月)
- 「はにわ」 (8)
- 「内藤礼」 (4)
- 「大覚寺」 (6)
- 「拓本のたのしみ」 (4)
- 「明末清初の書画」 (1)
- 「江戸☆大奥」 (7)
- 「法然と極楽浄土」 (5)
- 「神護寺」 (8)
- 「蔦屋重三郎」 (3)
- 「運慶」 (8)
- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)
- 「やまと絵」 (6)
- 「中尊寺金色堂」 (8)
- 「京都・南山城の仏像」 (4)
- 「古代メキシコ」 (6)
- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)
- 「東福寺」 (6)
- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)
- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)
- 研究員のイチオシ (572)
- 催し物 (87)
- news (340)
- 特集・特別公開 (236)
- 海外展 (1)
- 特別企画 (31)
- 東京国立博物館創立150年 (18)
- 絵画 (45)
- 彫刻 (91)
- 刀剣 (2)
- 書跡 (53)
- 工芸 (30)
- 考古 (82)
- 中国の絵画・書跡 (79)
- 教育普及 (105)
- 保存と修理 (23)
- 調査・研究 (6)
- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)
- トーハクよもやま (4)
- 博物館でお花見を (21)
- 博物館に初もうで (26)
- 博物館でアジアの旅 (45)
- 展示環境・たてもの (48)
- 2022年度の特別展 (31)
- 2021年度の特別展 (21)
- 2020年度の特別展 (14)
- 2019年度の特別展 (46)
- 2018年度の特別展 (34)
- 2017年度の特別展 (37)
- 2016年度の特別展 (54)
- 2015年度の特別展 (58)
- 2014年度の特別展 (50)
- 2013年度の特別展 (67)
- 2012年度の特別展 (64)
- 2011年度の特別展 (45)
- ウェブおすすめコンテンツ (19)
- ロケ情報 (2)
- 秋の特別公開 (11)
- トーハク140周年 (16)
