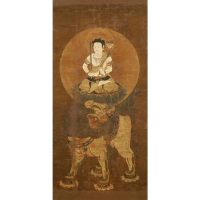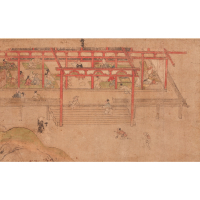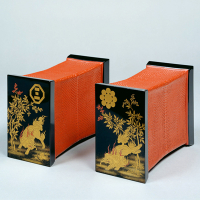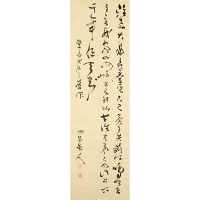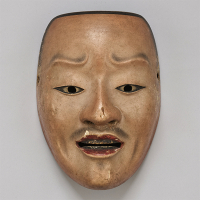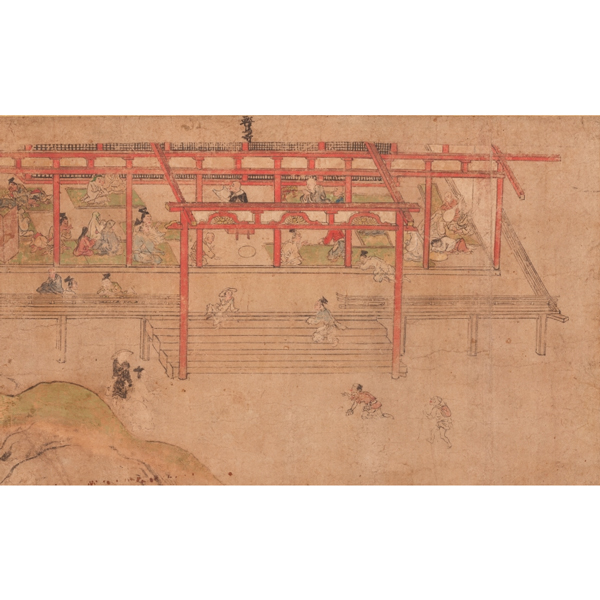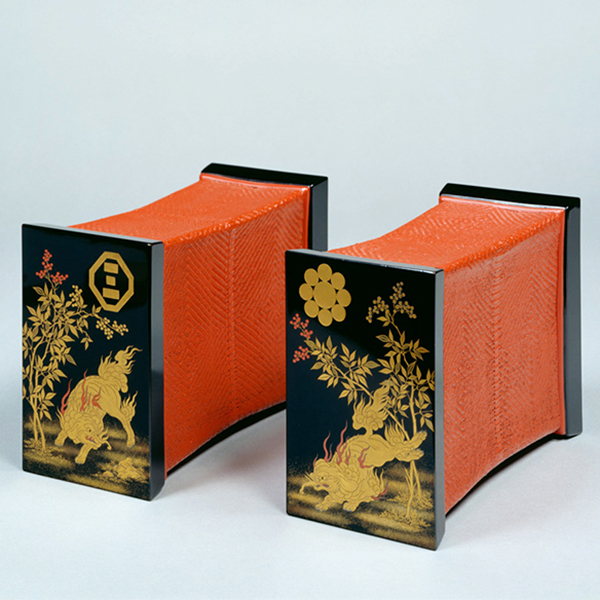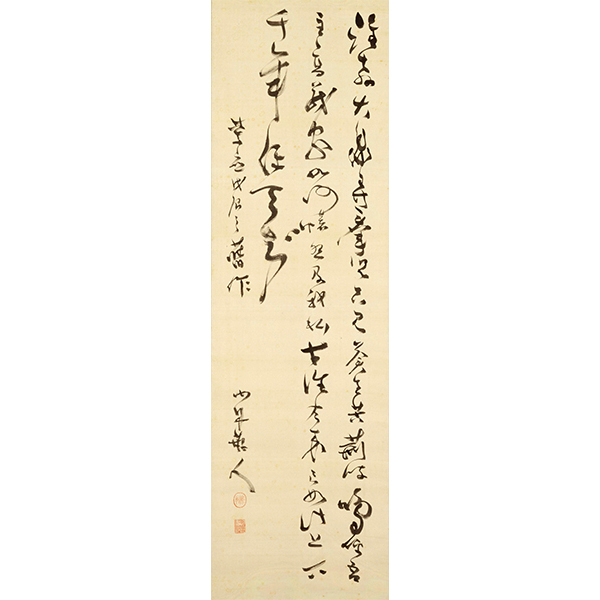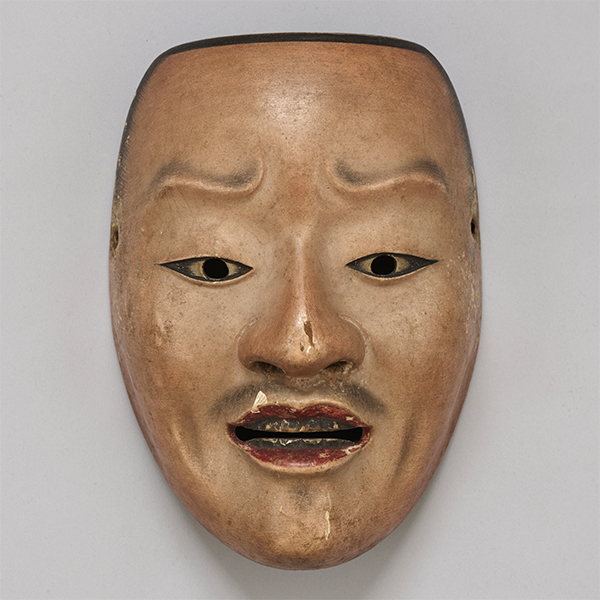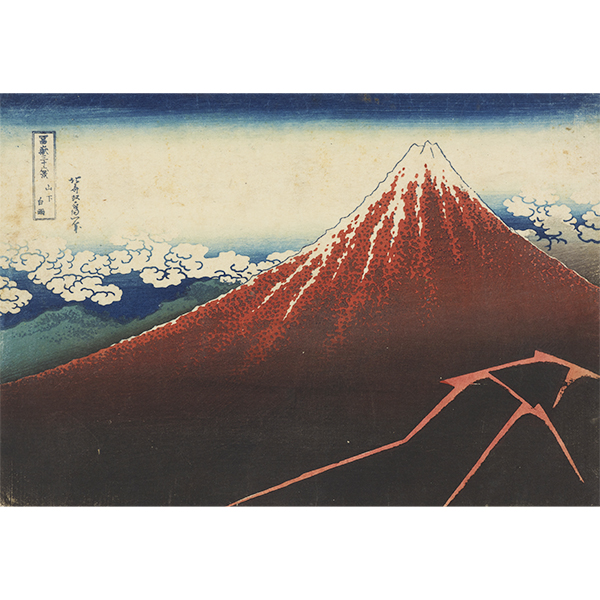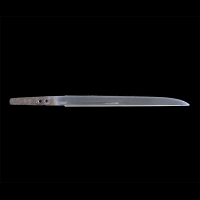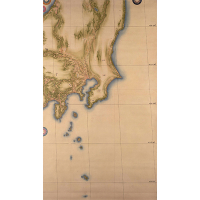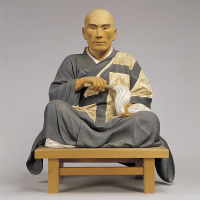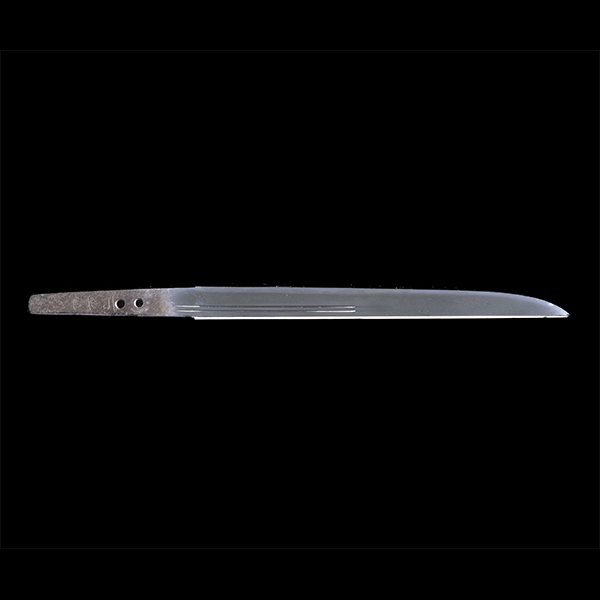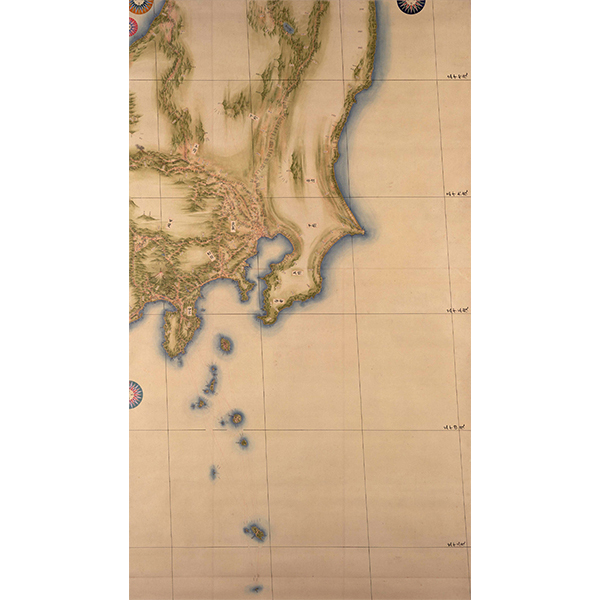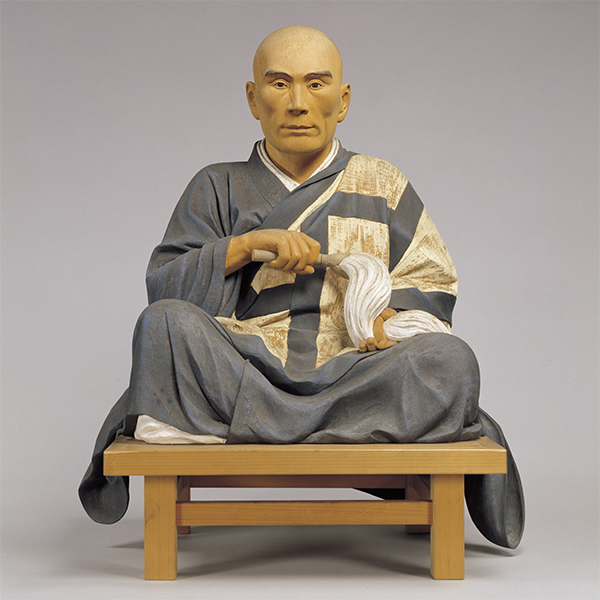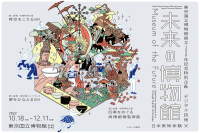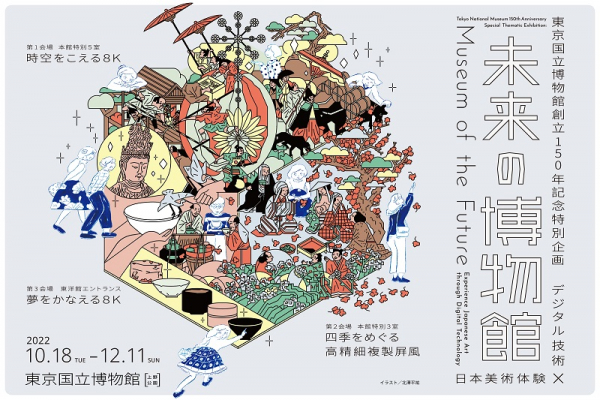日本美術のあけぼの―縄文・弥生・古墳
2階 日本美術の流れ
1室
2022年7月5日(火) ~
2022年12月25日(日)