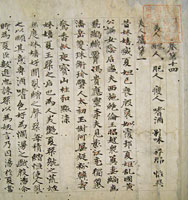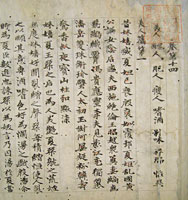日本美術のあけぼの ―縄文・弥生・古墳
2階 日本美術の流れ
1室
2005年9月6日(火) ~
2006年2月26日(日)