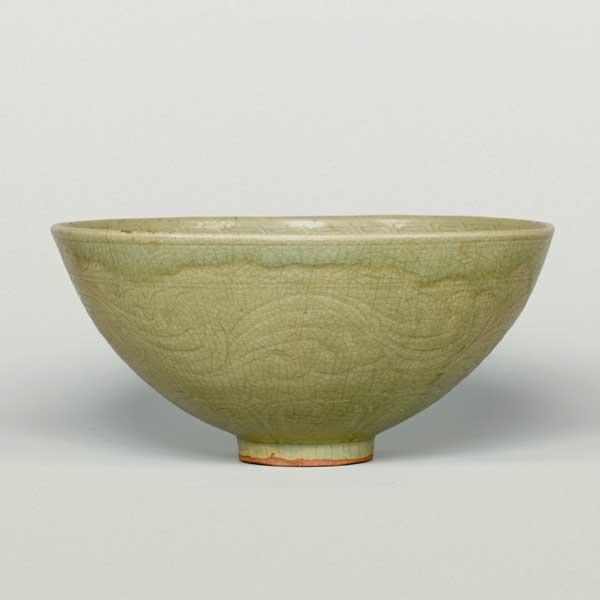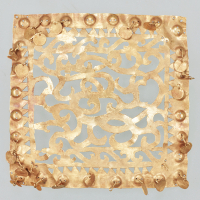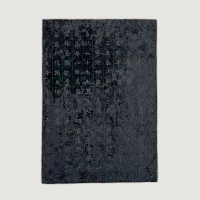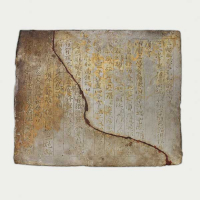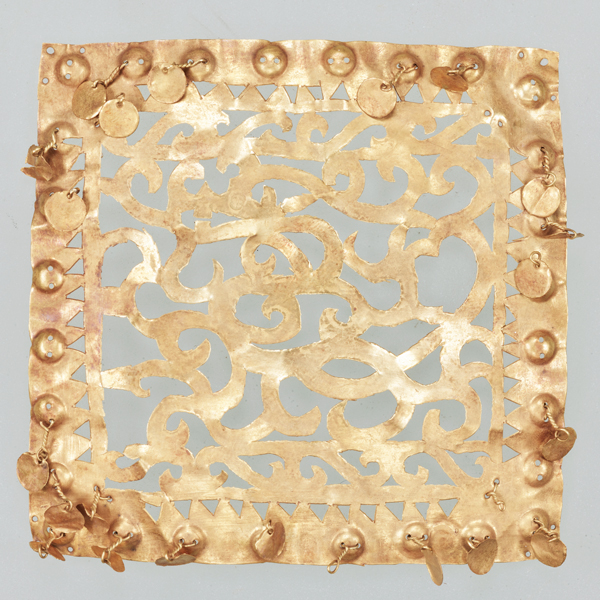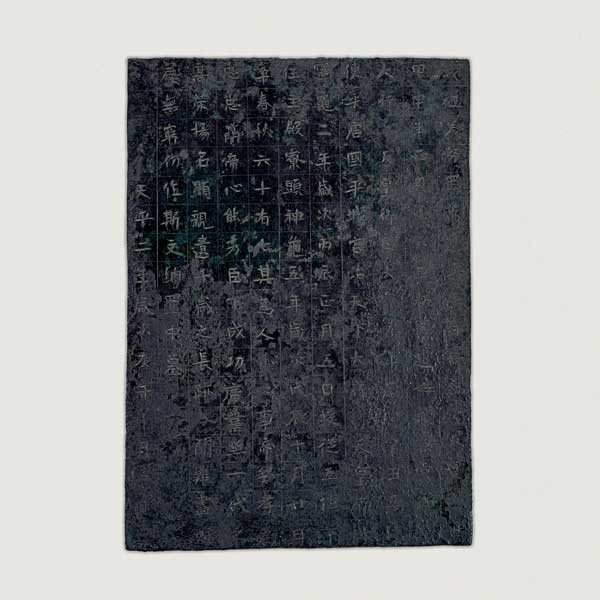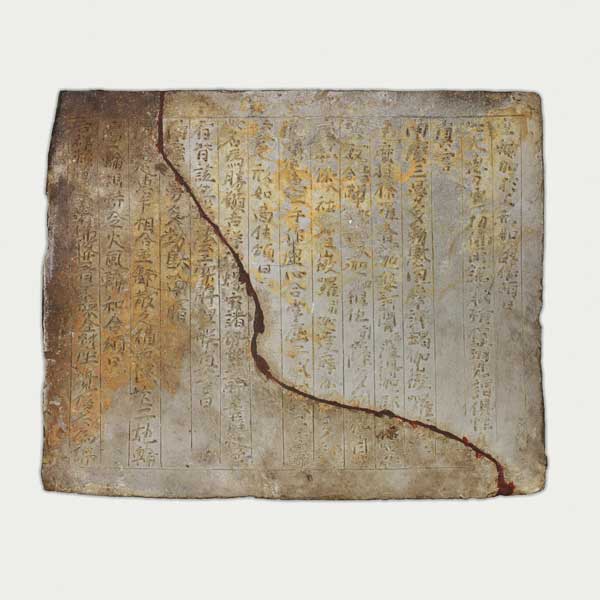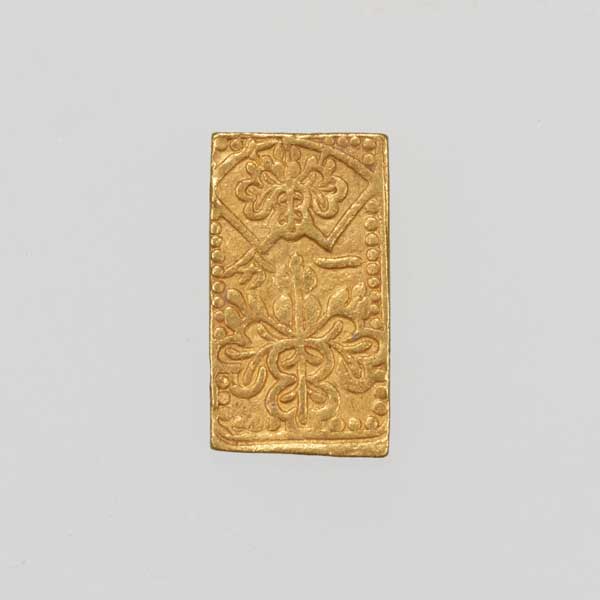氷河期の日本列島に暮らした人びと―道具作りのはじまり―
1階 日本の考古(通史展示)
考古展示室
2022年9月6日(火) ~
2023年3月5日(日)