館長メッセージ
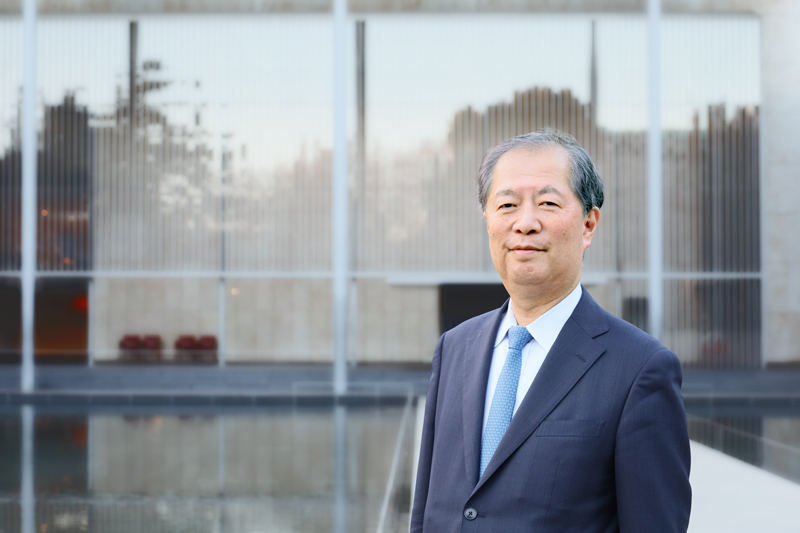
みなさま、ようこそ東京国立博物館へ
東京国立博物館長の藤原誠です。
東京国立博物館は現在、多くの国内外のお客様にお越しいただき、コロナ禍以前にも増して活気に満ちています。
皆様の博物館に対する興味関心が高まっていることを実感させていただくと共に、研究員や職員が一丸となって取り組んできたことが表れ始めた、そんな感想を抱いています。
私は昨年春に2つのスローガン「持続可能な博物館」「世界に冠たる博物館」を掲げ、さらに11月には、これを計画的に達成するべく、『東京国立博物館2038ビジョン』を発表しました。
本館のオープンから100周年となる2038年に向かって、「創造力を剌激する博物館」「共に創る博物館」「みんなが来たくなる博物館」「日本と世界をつなげる博物館」のテーマとそれに沿ったロードマップを策定し、皆様と「共に創る最先端ミュージアム」として成長することを目指しているところです。
これまで先人たちが築き上げた博物館のレガシーを踏まえ、安定した財政基盤の確立、先端技術の積極的な活用、多面的なリスク管理をはじめとする経営戦略によって博物館マネージメントを抜本的に見直し、人類共通の宝を未来まで確実に届ける持続可能な博物館となること。
日本発の文化拠点の役割を果たすべく、世界のミュージアムとのネットワークを強化。博物館が地域に根差し愛され、多くの方々に利用していただくと同時に、我が国を代表する博物館として、インバウンド対応の充実や海外展の実施を含め、世界のミュージアムをリードする博物館となること。
旧来のやり方にとらわれず、柔軟で革新的な思考と実行で「持続可能な博物館」「世界に冠たる博物館」を目指して参ります。
“いにしえから宝物を創ってきた人々の想いを、今を生きる力にする”、この言葉に私たちの価値観と使命を込めました。これからも、2038年に向けて躍動を誓う東京国立博物館にご期待ください。
2025年4月
東京国立博物館長
藤原 誠
東博館長日誌
東京国立博物館メールマガジンで連載中の東博館長日誌バックナンバーをご覧いただけます。
最新話
第10回
こんにちは、東博館長の藤原です。
早いもので、この東博館長日誌を連載してから、今回が10回目となりました。今回は、主に学芸部門で、より成長できる余地があると強く感じている点について、お話ししたいと思います。
東博の学芸部門の専門性は、我が国の博物館の中で最高峰であることは誰も異論がないと思います。このことは、明治5年の東博創設以来、政府が学芸の分野で優秀な人材を集め、彼らが東博で切磋琢磨してきた長い伝統による蓄積があったからでしょう。
一方で、組織として前進するためには改善が必要な点も明らかになってきました。
最近、学芸部門の職務において、外部の関係先から貴重なお申し出やご依頼をいただく中で、その対応において、当館内部の手続きが想定以上に滞る事例が複数発生しました。こうした状況を踏まえ、相手方の思いを丁寧に受け止め、円滑に対応するためには、事務手続きの流れや担当間の連携をより明確化し、スムーズに進められる仕組みを整えることが不可欠だと強く感じています。
私としては、このような事例は、専門性の高さに比べて組織人としての意識が十分に追いついていないことが一因であると分析しています。その結果、学芸部門にガバナンスが十分機能していないのではないかという強い懸念を抱きました。そこで、学芸部門全職員を対象にアンケート調査を実施したところ、具体的な課題が見えてきました。
たとえば、館内グループウェアのスレッドで、他職員への配慮を欠いた指摘が書き込まれていること。特定の職員に業務が集中して、業務負担のアンバランスが生じていること。出張・休暇・テレワークなどで職場にはほとんど来ていない職員が存在していることなどです。
東博に勤務する学芸部門の研究員は、冒頭申し上げたとおり、専門性はとても高いのですが、社会常識や組織行動の面では不十分な面も存在するということがよく分かりました。
日本にあるミュージアムのフラッグシップである東博は、今後とも国内外で強いリーダーシップを発揮し続ける使命を持っており、その役割を果たすには学芸部門のガバナンス強化は欠かせません。東博館長として私は、学芸部門の幹部とも協力しつつ、そのガバナンスの確立を図っていくことに強い覚悟を持っているところです。
バックナンバー
第1回
こんにちは、東京国立博物館長の藤原誠です。 私が東京国立博物館(以後「東博」とします。)の館長に就任してから早くも2年9か月が経過しました。これまで東博で仕事をする間に、私にとって未知なる様々な体験をしてきたので、それらを振り返りつつ、日々の出来事を紹介するコラムをこのメルマガに連載することで、東博の実情を広く皆様にお知らせし、御理解と御支援を賜りたいと思っています。
私は2022年6月に東博に着任しました。着任の翌日には、当時開催していた沖縄復帰50年記念の特別展「琉球」に皇族が御成りになられました。まだ館内の右も左も分からない中、ご先導のお役を拝命したため、館の総務課長に“先導役の先導”を務めてもらい、どうにか任務を果たすことができました。
その後は、ちょうど2022年が東博創立150周年の記念の年であったので、10月18日から開催の特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」や、11月7日開催の150周年記念式典などの準備作業に多くの時間を費やしました。これらの行事は、関係する館員の協力を得て、滞りなく実施することができたところです。
この頃の自分を今から振り返ってみると、目先の懸案事項の処理で精いっぱいという状況で、館全体を俯瞰的な観点で見回して仕事を進める余裕はほとんどなかったのではないかと感じています。
このような状況の中、ロシアのウクライナ侵略に伴う光熱費の高騰が東博にもジワジワと影響を与え始めていました。この問題について私がとった行動については、次回のメルマガで詳しく紹介します。どうぞお楽しみに。
第2回
2022年6月の館長就任後、まだ各部署からの所管事項説明を受けているような段階で、7月の館内運営会議にて経理担当から電気ガス料金の著しい増加についての状況報告があり、館内における支出削減の自助努力だけでは対応が難しい状況にあることが判明しました。電気ガス料金の高騰は、ロシアによるウクライナ侵略が主要な原因となっており、この問題がある程度続くことが見込まれたところです。そこで私からは、他の国立博物館・美術館と連携を取りつつ、国に補正予算を求めることを検討するよう指示を出しました。
そのような中、年末に向けて国による予算措置が財務省の抵抗でなかなか認められない方向性が感じ取れたため、月刊「文藝春秋」という雑誌に博物館の危機的な財政状況を訴える投稿をすることを決意しました。この投稿は翌2023年1月発売の同誌2月号に掲載され、一時はYahooニュースのトップに躍り出るなど社会的に大きな反響を呼びました。これを受けて一時期、個人からの東博賛助会員への申し込みが激増するというすばらしい反応がありました。
しかし結局のところ2023年度政府予算には、電気ガス代の高騰に対応する予算が国立博物館・美術館に対しては措置されずに終わりました。そこで私としては、何とか少しでも予算措置がなされるよう関係方面に奔走した結果、同年半ば頃には、東博が国立機関であるにかかわらず、史上初めて東京都の補助金を少額ですが獲得することが決まりました。この過程では、関係者の理解を得ていくのに労を費やしましたが、ここでは詳細な説明は控えたいと思います。
これと並行して、高額の賛助会員の積極的な勧誘、観光庁などからの補助金の積極的な獲得にも注力したところです。その結果、2023年度の賛助会員会費収入は前年度より3割以上増加しました。また、観光庁の観光再始動事業として約8千万円の事業費を獲得しました。
このようにして、東博の財政的な危機は当面どうにか乗り切った次第ですが、館長着任してからの1年間、今回説明したような様々な努力をする過程で、東博の内在的な問題点が私には見えてきました。これについては次回のメルマガで詳しく説明しますので、少しの間、お待ちください。
第3回
こんにちは、東博館長の藤原です。
東博館長の就任時に前任者から引継ぎを受けましたが、その内容は人事とハラスメント防止が中心であり、事業面については好きなようにやれば良いと言われた程度でした。そこで、私自身は博物館行政の経験がない全くの“シロウト館長”であるため、しばらくの間は館内の様子をじっくりと観察していく覚悟を決めました。
すなわち、館内の各部署での業務の動向を注視しつつ、館の全体像の把握をすることに静かに努めていたところです。しかしながら時々は、新たな気付きの点があれば、新規対応の指示を担当職員に対して出すことがありました。
ところが、私が指示を出すたびに、職員から返ってくる答えの大半は「予算がないのでできません」「職員が足りないのでできません」という内容ばかりであり、積極的な姿勢や改革精神を感じることは、ほとんどありませんでした。
具体例を挙げると、東博を各方面に対して一層アピールすることで知名度を高めたいと考えて、ブランディング戦略の一環として「東博アンバサダー」制度を新設し、著名人にアンバサダーを依頼したいと館内で私から提案しましたが、最初に返ってきた担当の反応は「そのような予算的な余裕はありません」という冷たいものでした。おそらく担当には、著名人に東博を宣伝してもらうことで来館者や施設利用イベントが増えて、その結果として自己収入が増加して新たな事業展開のための予算的余裕が生まれるという発想がなかったのだと思います。あるいは、そもそも新しい仕事は忙しくなるので、担当として受けたくなかっただけなのかも知れません。そこで私からは「お金がないならば、私が自分で著名人の方にボランティア・ベースでの東博アンバサダーをお願いする」としたうえで、その後順次、建築家の隈研吾さんなどに依頼して東博アンバサダー就任の了解を取り付けていきました。
また、前回ご紹介した光熱費問題についても、担当している当時の経理課長や総務課長は深刻な状況を理解した上で機敏に動いてくれましたが、東博が財政面で危機的状況に向かっているという問題意識を館全体で共有するという雰囲気は全くなかったところです。
他方、東博では運営会議という幹部会が1か月に2回程度開催されており、ここでは、常設展や特別展の展示案、施設貸出によるイベント予定などの確認、事務的な規定改正案などの議題を審議・報告しておりました。
ご承知のとおり、東博が実施している常設展示や特別展のレベルは極めて高く、各方面から評価を受けていることは言うまでもありません。したがって、これらを議案として、日々のオペレーションを決めるこの運営会議の役割は、極めて大きいところです。しかし、ここでの議論は、あくまでも日々のオペレーションにとどまっており、東博としての戦略を議論することは残念ながら全くなかったのです。
そこで、まず2023年1月末の運営会議で、来館者数や施設利用イベント数などを増やすことで自己収入を増加させるために、「東博のブランディング戦略」を検討するように私から指示を出しました。
また、東博では日々の事業などのオペレーションはしっかりと進めているが、そこには自己収入や寄附金などの外部資金を増やすことで新たな事業展開を実施していくための「経営戦略」が欠如していると感じたので、同年4月冒頭の運営会議では、私からその検討開始を指示しました。
このあたりが私の現在進めている「東博改革」のキックオフと言えましょう。しかし、この「東博改革」の道は容易なものではありませんでした。その話はまた次回としましょう。
第4回
こんにちは、東博館長の藤原です。
前号でご紹介した私の「東博改革」について、これから順次、説明したいと思います。
まず第1は東博の経営体制の確立です。
2023年4月の運営会議で「東博は経営戦略や民間的発想が不十分な現状を踏まえ、入館者数や収入額などの重要な数字を幹部で共有した上で対応策の検討が必要だ。」と私から指示を出しました。しかし、展覧会の展示内容などの日々のオペレーションを協議する運営会議で、上記のような経営問題を実質的に検討するのはなかなか難しいことが判明しました。
また、この運営会議も、慣習的に7月下旬から9月中旬まで1か月半の間、全く開催されないありさまでしたので、同年9月の運営会議では「経営問題を担当する経営企画室を年内に立ち上げて、戦略的に対応できるようにすべし。」と指示を出しました。これを受けて同年11月には経営企画室が館長直轄の組織としてスタートしましたが、この段階では同室メンバー全員が関係課職員との併任であり、同室があまり機能しない状況が続いたので、私から改めて専任職員の配置を強く求めました。
その後、翌2024年1月からは、運営会議とは切り離した経営戦略会議を新たに設けて、東博の経営戦略を議論する場を置きました。そして適性を見込んだ総務課の職員1名が経営企画室の専任職員として任命されたので少しは状況が変わるかと期待したのですが、同人の座席は引き続き総務課の執務室内に置かれたために総務課のルーチン業務も任されてしまい、なかなか経営問題について集中して仕事を進めることができませんでした。
そのため、経営企画室に独立した執務室を確保することと、経営問題やファンドレイジングに精通した人材を民間から登用することを担当に対して指示しました。その結果、同年4月からは、先の専任職員に加えて新たな事務補佐員1名が採用され、7月までに経営企画室の執務室が確保されました。その後、公募によって民間から室長やファンドレイジング担当など計3名を順次採用し、同年10月には現在の体制が完成したところです。これにより、東博の経営戦略の推進体制が格段に向上しました。その成果については、いずれご紹介したいと思います。
今から振り返ってみると、民間では当たり前の経営企画室という経営体制の確立について、これほどのまでの時間がかかった理由としては、東博の幹部職員がそもそも「経営」という意味を理解していなかったのではないか、ということでしょう。東博の歴史は153年という、我が国では最も長い歴史を持つ日本を代表する博物館ではありますが、創設以来ずっと「国立」であり、平成の途中で独立行政法人化しましたが、職員の意識は依然として公務員のままであるため、国からの予算に依存しきってしまい、自らの努力で収入をあげて事業を拡大発展させるという経営的な発想を持っていなかったのではないか、ということです。
第2は職員の意識改革です。
前号で、東博職員には「積極的な姿勢や改革精神を感じることはほとんどありません」と書きましたが、実はいくつかのルートで「若手の中にはやる気がある人はいるが、内部のヒエラルキーで保守的上司からストップがかけられている」という情報を私は入手していました。
そこで2023年4月には、職員のモチベーション向上策を検討するよう担当に指示を出しました。これを受けて新たに設けられたのが(1)新規事業アイデア提案の仕組み、(2)館長賞表彰制度の2つであります。
(1)については、2024年2月に最初の審査委員会を開催し、複数の提案をヒアリングした結果、広報室の若手女性職員からの提案「『子育て世代』来館促進プロジェクト」が採択され、必要な予算配分を決定しました。
これはきわめて画期的なことで、若手職員が所掌分野にとらわれず、時代を先取りした新鮮な発想で事業案を企画して、それを館長・副館長・各部長の承認を受けて実施するというものです。従来の古い体質の東博、すなわち若手の新たな試みが現場で潰されてしまうという職場環境では、およそあり得なかった新たな仕事の進め方となりました。
その後、このプロジェクトは同年11月実施の「あそびば☺とーはく!」のイベントとして結実し、全国の博物館・美術館から多くの視察団が来るほどの関心が示される、とても先進的取り組みとなりました。
その後、2024年9月には2回目の審査委員会が開催され、その結果、意欲ある学芸の研究員と国際担当の職員などからの提案である「東京国立博物館における作品解説ガイドライン策定」が採択されたところです。
これも従来の学芸の現場では消極的な対応であった事項について、海外の先進的なミュージアムでは策定が進んでいるものを東博としてキャッチアップしようという意欲的な取り組みでしょう。
先の(2)の館長賞表彰制度については、(1)の新規事業を採択された提案者、あるいは卓越した学術研究論文がジャーナルで採択された者、ほかにも業務改善や改革で大きな成果を出した職員などを対象に、東博への高い貢献を示した優秀職員として選考、表彰して、彼らに対して必要な研修費を支給するなど一層の支援を図る仕組みです。
以上のような改革によって、以前と比べて若手職員が生き生きと仕事ができる環境が東博内で整えられつつあると思っています。今後とも、優秀でやる気がある職員を支えることで、これまで歴史と伝統に安住して改革の努力を怠ってきた東博について、そのあり方を抜本的に変革して、国民の期待に的確に応えることができる組織を作り上げていきたいと考えています。
第5回
こんにちは、東博館長の藤原です。
今回は東博改革の一環として私が現在進めている国際戦略の強化についてご紹介しようと思います。
私が館長に就任した約3年前(2022年半ば頃)は、世の中がまだコロナ禍にあったため、海外との交流は極めて限定的でした。時折来館する海外の博物館・美術館関係者の挨拶を受けてくれとの話が、国際担当から上がってくる程度であり、私は単にその接遇を務めるというのが館長の役割なのかと当時は単純に思っていました。
しかし、その約1年後の2023年6月初めにはコロナ禍も収束して、東博が主催する海外展をギリシャ・クレタ島のイラクリオン考古学博物館で開催することとなり、その開会式に出席するために私も当地に出張する機会を得ました。
この展覧会は考古を中心として出品する「日本展」でしたが、そもそも2016年に東博で開催した特別展「古代ギリシャ―時空を超えた旅―」のお返し展としての意味合いを持っているものでした。本来は2020年4月に開催すべく準備を進めていましたが、コロナの流行によりやむを得ず延期になっていたものです。
この出張には奈良国立博物館の井上館長もご一緒でした。最初はなぜ奈良博館長が来られているのか不思議でしたが、事情を伺ってみると、先の古代ギリシャ展の開催を東博副館長として仕掛けた張本人でいらっしゃるということが分かり、なるほどと思いました。
その際に井上館長から、文化庁が主導して財源を確保し、東博が中心となって海外展を実施してきた経緯や現状について、詳しくお教え頂いた次第ですが、私がもっとも驚いたのは、国主導の海外展については、ギリシャで開催するこの展覧会が最後であり、国における予算措置が今後の海外展については全くなされておらず、具体的な海外展の計画は全くないという点でした。
コロナ禍前は、政府としてインバウンドの大幅な拡大を目指していたところで、そのためにも、国が主導して海外展を開催し、日本文化に対する関心を高めることで日本へのインバウンドにつなげることは理にかなったものといえましょう。コロナ禍の期間中それが停滞するのは仕方がなかったでしょうが、井上館長からの情報提供により、文化庁や東博として、コロナ禍後のインバウンド拡大に向けて何ら手を打っていないということが明らかになりました。
そこで帰国後さっそく、私は館内関係者に対して、海外展の実施に向けて準備を進めるように指示を出しました。ところが館内から返ってきた答えは「そんなことをする予算がありません」「忙しいので文化庁からの応援がないと手が回りません」といった“恒例のネガティブ反応”ばかりでした。
このままでは東博として動く気配が全くないため、私は文化庁幹部に対してこのような実情を説明した上で、従来のように海外展を実施するための予算の確保を求めました。幸い、現在の文化庁の体制は都倉長官以下極めて積極的に対応してくれる幹部が揃っているため、この件はとんとん拍子で進んで、最終的には日本芸術文化振興会に所要の予算が計上され、助成金の枠組みができました。このように予算的な後ろ盾ができたことで、東博としてこれからも海外展を企画できる次第です。
また、スタッフ不足の問題は、海外展室を新設した上で、そこに専任の職員を再配置したり、新たなスタッフを採用するなどして体制の強化を図りました。
その結果、まず本年中にインドネシアのジャカルタで東博の海外展を実施する運びとなり、現在、精力的に準備が進められています。また、来年後半にはメキシコでも東博の海外展を開催する予定です。その後についても、ヨーロッパやアメリカなどでの実施をすべく水面下で動いています。
国際戦略の強化についてはこのほかにも取り掛かっているものがございますが、続きは次回にしましょう。
第6回
こんにちは、東博館長の藤原です。
前回に引き続き、東博の国際戦略強化について話題にしたいと思います。前回は東博が国外で実施する海外展について説明しましたが、今回のテーマは、東博による海外の博物館・美術館との連携強化です。
私が館長に着任した約3年前の時点では、東博として組織間で連携協定を結んでいる相手方はわずか3館に過ぎませんでした。具体的には、中国の故宮博物院と上海博物館、韓国の国立中央博物館の3館です。当時、私から担当者に対して「日中韓の間の連携も重要だが、なぜこれら3館としか組織的な連携をしていないのか?」と尋ねたところ、返ってきた答えは「中国や韓国にある文化財は、東博研究員の研究対象に値するものが多いので交流を進めるメリットがあるが、他の国との交流にはそのメリットをあまり感じないからだと思う」という趣旨のものでした。
しかし、たとえシロウト館長である私であっても、この説明は腑に落ちなかったので、じっくりと時間をかけて考えてみることにしました。
たどり着いたのはまず、従来の東博の最大の問題点は、国際交流が個々の研究員が中心となっており、そこには組織全体として多角的に館どうしの交流を進めていこうという視点が欠けていたことです。
確かに個々の研究員は科研費などの研究費を活用して、必要があれば中韓以外に欧米などの博物館・美術館に出張することにより、必要な調査研究を進めることができます。そのことにより、研究員や学芸員どうしが国際的につながることは可能となるでしょう。しかしながら、このような交流は基本的に属人的なものに留まり、どちらかが異動や退職で当該組織から離れた場合には、たちまち交流が途切れてしまいます。その結果、そこには組織間の交流に関するレガシーは何も残らないということになります。
例えば、昭和49年(1974年)に東博で開催された「モナ・リザ展」は素晴らしい実績をあげましたが、このような絶好の機会に、当時の東博はルーブル美術館と組織的な関係を築くことをやらなかったため、現在では同館との関係性はまったくと言っていいほど存在しない残念な状況になっています。
やはり、東博は日本を代表する博物館である以上、それぞれの国を代表する博物館・美術館やアジア美術関係の館との間では、組織間の永続的な連携協定を結んだ上で、単に研究員の調査研究のみならず、展覧会の相互開催や文化財修復支援など多面的・重層的な交流を推進すべき責務があるはずです。これまでの東博には、このような国立館としての責務をきちんと果たしていこうという認識や覚悟が不足していたのではないでしょうか。
次に、海外の博物館・美術館で日本美術の作品をそれなりの規模で所蔵しているところは結構あります。それらの館には、必ずしも日本人ではありませんが、日本美術を担当する学芸員が働いています。彼らは日本留学経験があり、日本語を話す人も多く、総じて親日的です。このような博物館・美術館との間で東博が組織間の連携協定を結んで交流を深めていけば、交流先の日本美術担当学芸員の地位がその組織内で相対的に上がり、その結果として日本美術に対して一層の重点を置いた事業展開が、先方の館でなされていく可能性が高まるといえましょう。中国や韓国の国立博物館では、このようなアプローチで欧米の博物館・美術館における自国文化のアピールを進めているようですので、東博もモタモタして後れを取っている場合ではありません。
なお、東博が実施している素晴らしい事業について、ここで触れておく必要があります。それは、2014年度から実施している「ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業」です。当初は、アメリカ、カナダおよびヨーロッパの地域を対象に「北米・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業」としてスタートしましたが、現在はアジア・オセアニアなど地域を拡大し、北米・欧州の文字が取れました。この事業は日本美術の専門家ならびに日本の文化財を扱う人を日本に招いて、各々が抱える課題の共有と情報交換、そして人的ネットワークの構築を目指すものです。具体的な内容としては、日本美術とその保存・活用に関する専門家会議とワークショップやシンポジウムの開催や、その年のテーマに合わせた国内の著名な美術館・博物館や伝統技術の工房などへのエクスカーションなどです。この事業の最大の功績は、東博の研究員が海外の博物館・美術館で日本美術を専門にしている学芸員と知り合うことで個人間のネットワークを形成することができるということです。
この事業のベースがあったことで、私が館長に就任して以来積極的に取り組んできた、海外の博物館・美術館との組織間連携の構築をスムーズに進めることができた次第ですが、この件については、次回、詳しく紹介したいと思います。
第7回
こんにちは、東博館長の藤原です。
これまで2回にわたり東博の国際対応について説明してきました。今回は、海外ミュージアムとの組織間連携強化の推進について、もっと具体的にお話します。
前回ご説明したとおり、3年前に私が館長に就任した時点では、東博が組織間で協定を結んで交流を進めている相手方はわずか3館に過ぎませんでした。具体的には、韓国の国立中央博物館(2002年~)、中国の上海博物館(2007年~)と故宮博物院(2008年~)です。
これとは別に、日中韓3か国の国立博物館相互の交流を図る観点で、2006年から館長会議や共同展覧会を開催するスキームもあります。ここには、日本から東博、中国から中国国家博物館、韓国から国立中央博物館がそれぞれ各国を代表して参加しています。当初は毎年開催していましたが、最近では隔年開催となっています。
もちろん日中韓の関係がとても重要であることは言うまでもありませんが、日本の博物館で頂点にある東博が国際活動の面で北東アジアのみでしか活動していないというのは、おかしな話でしょう。東博は本来であれば、この国を代表して世界中の主要なミュージアムとの交流関係を結ぶべきです。私はこのような問題意識をもって、コロナ明けの館長2年目以降、積極的な活動を始めました。
まずはマレーシアのイスラム美術館です。同館とは、東博で2021年に開催された特別展「イスラーム王朝とムスリムの世界」をきっかけとした現場レベルでの交流という土台があり、また、マレーシア駐在経験がある元商社マンによる仲介の労力も頂いたため、私が同館を2023年12月11日に訪問し、包括連携に向けてのMOU(基本合意書)を締結できました。これをキックオフとして、現在、相互に相手館における展覧会を開催できないかなど協議を進めているところです。
ちょうど私がマレーシア滞在中の翌12日に、イスラム美術館創立25周年式典が開催され、私も参加させてもらいました。その式典ではアンワル・イブラヒム首相が祝辞を述べられ、さらにそれに引き続く歓迎晩餐会にも同首相が出席されていました。日本政府と比較して、マレーシア政府の文化への力の入れ方の違いがよく分かる出来事でした。
次が香港故宮文化博物館(以下、香港故宮)です。同館が主催する香港国際文化サミットが2024年3月に開催され、そのパネルディスカッションに私も招待されて参加しました。この博物館は香港返還25周年を記念して2022年に開設された新しいところではありますが、北京の故宮博物院から約千点近くの作品を借り受けており、中国としてこの博物館の発展に注力しているようです。私の訪問時には、アジア地域のみならず欧米も含めた世界各国の主要なミュージアムの館長も招待されており、東博も含め多くのミュージアムが香港故宮側とMOUを結びました。これを受けて東博では現在、香港故宮との間で具体的にどのような事業展開ができるのかを相談しているところです。
まだ設立からの歴史がまだ浅い香港故宮ですが、国を挙げて世界中の主要な博物館とMOUを締結し、香港故宮を積極的に売り込もうとする熱意を感じた次第です。
次が米国のスミソニアン博物館機構にある国立アジア美術館です。2023年10月に同館のロビンソン館長が東博を訪問した際に私から両館の連携強化を図るべくMOUを締結しないかと提案し、先方も了承しました。その後、私が翌2024年4月に先方を訪問して、MOUの締結に到りましたが、その際に両者の間では半年に1回は直接会って話をしようということで一致しました。実際、同年10月にはロビンソン館長が来館し、また本年2月には私が再び先方を訪れるなど、ほぼ半年に1回は実際に面談して、連携協力の具体策の協議を進めているところです。
それから現在まで、アジア、欧米を中心に各国の博物館・美術館とのMOU締結を積極的に進めており、9月末現在で既に21館との締結がなされています。さらに中東や中南米などの館ともMOUの締結に向けての話し合いを進めています。
私としては、このように世界の主要な博物館・美術館との関係を強化することを土台として、2028年頃には東博が主催する世界館長会議を東京で開催し、東博がMOUを締結している各館を中心に参加してもらい、海外ミュージアムとのネットワークを強化するとともに、我が国の素晴らしい文化を世界に発信する絶好の機会としたいと思っています。
第8回
こんにちは、東博館長の藤原です。
最近は3回続けて国際戦略をテーマにご説明してきましたので、今回は再び、東博のオペレーション関係に話を戻したいと思います。
まず、東博の予算上、「館長裁量経費」という項目が計上されていますので、これについて説明したいと思います。
この名称だけみると、館長である私自身が自由に何でも使えるように思われる方もおられるかもしれませんが、実態は全く違います。現在の運用は、私の海外出張を中心とした出張に係る経費、寄付集めなどで様々な方を私が訪問する際の手土産の経費、さらには私が使用している携帯電話やWi-Fiの利用料金など、私が職務を遂行する上で必要不可欠な経費がここから支出されることとなっています。また、その支出については、適正な支出がなされているかを経理担当部署が定期的にチェックしています。
ところが、私が館長に就任した当時は、そもそもこの「館長裁量経費」について担当からきちんとした説明すらありませんでした。たまたま、ある支出について私の了解を取る事案があったことをきっかけに、この経費の存在が判明しました。
そこで、これについて詳しく調べていったら、結構、驚くような実態になっていました。すなわち、「館長裁量経費」であるにもかかわらず、職員が館長である私の了解を取ることなく、館長の活動に何ら関係ない事項に支出していることがわかりました。要すれば、既定の予算計上されている他の予算項目からでは支出できないような案件について、館長が知らないところで担当者が勝手にこの経費から支出しており、かつ経理担当部署の事後チェックも全く受けていなかったということです。これでは、「“館長"裁量経費」ではなく「“職員"裁量経費」と言われても仕方がないでしょう。
このような予算執行のあり方は、予算の不適切支出を招き、ひいては不正の温床になりかねないので、私は直ちに経理担当に改善を指導しました。その後一定期間が経ってから、再度、「館長裁量経費」の使途をチェックしたところ、全体としてはかなり改善していましたが、一部には依然として使途がよく分からない支出も散見されたため、改めて経理担当課長に直接かつ厳しく改善の指示を出しました。そのような経緯があって、現在は最初に説明したような適正な「館長裁量経費」の運用実態となっている次第です。
次に、数千万円から1億円以上の予算を支出すべき高額の大型契約案件のあり方についても説明しましょう。
東博では、空調設備をはじめとして老朽化している施設が多く、その更新工事が多く実施されています。また、最新の展示ケースなど展示関係の設備、あるいは文化財の調査のためのCTスキャン装置などの研究関係の設備などについて、購入契約も多く結んでいます。これらの契約では、数千万円から1億円以上の予算の支出を伴うこととなり、その財源については、国からの補助金のみならず、東博の自己財源も活用されています。
私が館長に就任した約3年前の東博の予算規模は約30億円でしたから、これらの契約金額は館全体の予算規模と比較して決して少なくはありません。ところが、これらの契約について、事業の必要性の有無の判断というスタート時点から、途中の公募のプロセス、契約金額などが館長である私に全く相談なく進んでいる案件が多いことが発覚しました。これも、職員の誰かがたまたま工事の話を私にしてくれたことがきっかけで了知した次第です。
そこで私から担当に対して、なぜ館長に相談なくこのような大型契約案件の仕事を進めるのかを問うたところ、驚くべき事実が判明しました。すなわち、東博の館内規程では、どんなに多額の契約案件でも、決裁権者は担当部長どまりとなっていて、規程上は館長の関与はあり得ないということです。つまり、自分たちはルールに従って仕事をしており、何ら落ち度はないという説明です。確かにルールはルールですが、わずか30億円程度の予算規模の組織で、そのトップの何らあずかり知らぬところで高額予算の契約が結ばれているというのは、ガバナンス上、普通の会社組織などではあり得ないことでしょう。このような事態を放置すると、館長の経営方針に合致していないような契約が平然となされてしまう懸念があります。
そこで私は直ちに、施設設備担当や経理担当に対して、1千万円以上の高額な契約が見込まれる事案については、その事業の必要性の有無の判断というスタートから最後の契約締結に到るまで、事前に館長への報告と相談を義務付けるよう指示を出しました。これ以降、現在まで新たなルールの下で運用されています。
このように高額契約案件のスタートから私が情報を把握することにより、従来ならば、ある設備について一定の金額を支払って購入していた事案について、も、交渉努力により、企業から東博への現物寄附という形でご提供いただけることになるなど、一定の成果を上げつつあります。
以上、代表的な2つの案件についてご紹介しました。このようなネガティブな問題の存在こそが、私が東博の経営・運営改革を開始したスターティング・ポイントだったと言っても過言ではありません。
さて、東博ではこのような問題事例だけでなく、職員が頑張っている事例もありますので、次回はポジティブな事例を紹介したいと思います。
第9回
こんにちは、東博館長の藤原です。
館長就任以来、私はこれまで東博の旧態依然とした体質の改革に邁進してきましたので、その実態と率直な感想をこの館長日誌で皆様に報告してきました。
ところが、先日、私と旧知で館長日誌を愛読されている方にお会いしたところ、「あなたの改革努力は評価に値するが、読んでいると自慢話にしか感じられない」との耳の痛い意見をもらいました。
確かに自らの改革努力をアピールするあまり、全てを自分でやっていると誤解されるような記述が多かったかも知れないと深く反省しました。というのも、館長としての私が推進する改革は、心ある東博職員のサポートと努力があってこそ成り立つものだからです。そこで、今回は東博職員が実際にがんばっている幾つかの事例をご紹介しようと思います。
まず初めに、10月下旬に私がインドネシアに出張した際の出来事についてご紹介します。
東博は今回、海外展開支援に関する文化庁の基金による助成を受けて、インドネシア国立博物館において染織関係の展覧会を11月1日から開催しました。その前日の10月31日に開会式があり、私はそこで開会挨拶をするために出張した次第です。この開会式では、インドネシアの文化大臣からも国内の出張先から駆けつけてまで祝辞を述べていただきましたし、司会はミスインターナショナルのインドネシア代表が務められたこともあり、とても盛り上がりました。
それはそれで結構なことでしたが、実はこの展覧会については、開会式前々日の10月29日夜まで、当初の予定どおりに開催できるのか全く見通せない状況だったのです。
展覧会の開催に当たっては、会場内で注意深く展示作業を行う東博の研究員チームの存在が不可欠であり、彼らは輸送した作品が開催地に到着するタイミングに、すなわち開会式の約1週間前には現地に赴き、毎日夜遅くまで会場であるインドネシア国立博物館で待機していました。
ところが何かの手違いで、間に合うように輸送されたはずの作品が、先方税関での通関作業がなかなか行われない事態となっていて、10月29日深夜になってやっと、税関からのゴーサインが出ました。
翌30日、つまり開会式の前日という中で、研究員チームが終日かけて展示を突貫作業で完成させることができたので、翌日の開会式が無事開催できた次第です。
このように慣れない異国の環境下で毎晩深夜まで待機させられた上に、最後は通常数日かけて慎重にやるべき展示作業をわずか1日で完成させるという超人的な対応をした、東博研究員チームの気力、体力、仕事ぶりは高く評価されるべきでしょう。
次に紹介したいのは、私が今年4月後半にUAEアブダビに出張した際の話です。実は4月の前半にUAEの文化観光局(DCT)長官(王族の一人)が東博を視察されたことがありました。私はその時は所用のためお会いできなかったのですが、対応した学芸部長の話では、東博の常設展示をとても気に入ってくれたので、今度、東博の館長がアブダビを訪問する際にはぜひとも会おうとの約束を同長官がしてくれたとのことでした。そこで私はもともとルーブル・アブダビなどへの出張予定が4月後半に入っていたので、その機会に同長官に会うべくアポ入れをしました。
ところが、同長官は本国では極めて多忙な方であり、アブダビ市内の移動でもヘリコプターを使っているほどとのことで、結局はアブダビ出張の最終日までアポが取れませんでした。その時点では私自身は半分諦めかけていましたが、出張に随行していた広報室の若手職員から「今晩のフライトまでまだ時間があるので、昼休み時間帯にDCTを訪問し、受付けにお土産を置いていきたい。そうすれば、もしかしたら長官にも会えるかも知れない。」との提案がありました。
そこで私も半信半疑でしたがDCTがある建物に行くことにして、出張者全員で取り敢えずその場に向かいました。私が車内で待機している間に、その若手職員が先の学芸部長と一緒に受付で東博のお土産を置こうとしたまさにそのタイミングで、同長官がモスクでのお祈りに向かうために玄関に出てきて、面識のある学芸部長を見つけて再会を果たしました。その連絡を受けて私もすぐさまそこに直行し同長官と会うことができました。東京での約束を果たすべく出張してきたと説明したところ、同長官はその場ですぐに部下の文化局長に電話をして、東博一行との打ち合わせをするよう指示し、そのまま外出されました。
この偶然の出会いがあったため、東博とDCTとの連携の話合いが一挙に進むことになった次第です。このような積極的な若手職員の機転が東博の海外交流の進展に大きく寄与したこととなり、称賛に値します。
今回、最後にご紹介したいのは、経営企画室職員の活躍です。この組織は、民間企業で営業活動や経営企画などの仕事経験がある3名の職員と、東博プロパーの職員1名、加えて、アシスタント1名の合計5名から構成されています。私が優秀だと感じる彼らと各部署の働きぶりの結果、寄付金額の大幅な増加、民間企業との協業の推進、経営課題の着実な進捗管理などが飛躍的に進んでいます。
以上、東博職員の素晴らしい活躍ぶりの一端をご紹介しました。もちろん、ご紹介したい事例はまだまだあります。このような私の仕事を支えている東博職員の今後の一層の活躍を心から期待しているところです。
